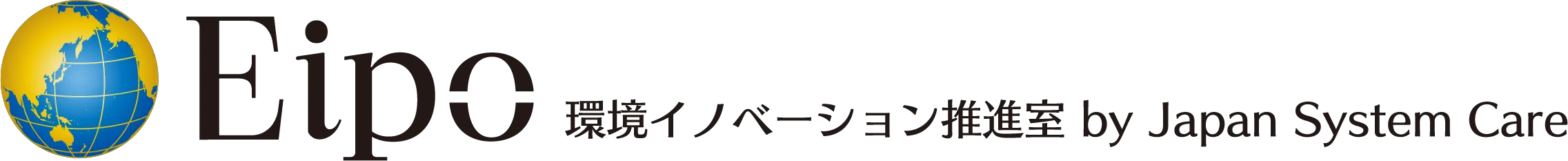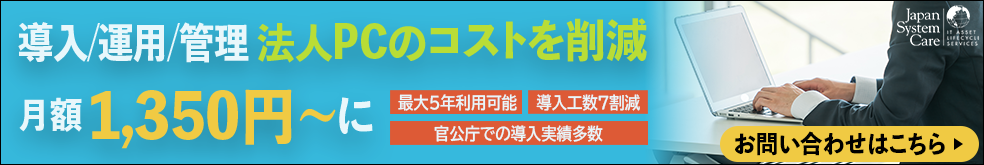目次
Windows11にアップグレードする条件

Microsoft社では、一定の条件を満たしたWindows10搭載のPCへ無償アップグレードを提供しています。ただし、PCのスペックや状況次第では、Windows11へ移行できない場合もあります。
まずは、Windows11への移行にあたって確認すべき条件を整理しておきましょう。
システム要件
Windows11には、次のようなアップグレード条件が存在します。Windows10よりも高スペックが求められるため、古い機種の場合は要注意です。下記を参考に、使用中のPCが要件を満たすかをチェックしておきましょう。
| ・1GHz以上で2コア以上の64ビット互換プロセッサー、もしくはSystem on a Chip(SoC) ・4GB以上のメモリ ・64GB以上のストレージ ・UEFI、セキュアブートに対応 ・TPM2.0に対応 ・DirectX 12以上に対応 ・9インチ以上、8ビットカラーの高解像度(720p)ディスプレイに接続 |
バージョン・空き容量
Windows11へアップグレードできるのは、バージョン2004以降のWindows10のみです。長期間放置されたPCでは、OSが古いバージョンのまま、すでにサポート対象外になっているケースもあるため、一度確認してみましょう。
他の注意点として、PCの空き容量があります。Windows11への移行には、HDD(ハードディスクドライブ)、SSD(ソリッドステートドライブ)に9GB以上の空き容量が必要です。
アップデート時に、「空き容量が不足している」といったメッセージが表示された場合は、下記の方法でPCの空き容量を確保しましょう。
| ・PC内の不要なファイルやデータを削除 ・ディスククリーンアップで、ブラウザやアプリなどが自動生成したファイルを削除 ・使用しないアプリケーションをアンインストール ・残したいファイルやフォルダを圧縮 ・外付けのHDDやUSBメモリなどに必要なデータやファイルを移動 |
Windows11のシステム要件を満たしているか確認する方法

使用中のPCがWindows11のシステム要件を満たすかどうかをチェックする方法として、次の2つがあります。
「Windows Update」のページを確認する
Microsoft社が提供する「Windows Update」は、セキュリティの強化を目的に、Windowsを最新の状態に保持する機能です。要件を満たしたPCであれば、Windows Updateを通じて、無償アップグレードの通知が届きます。
通知が届いていない場合も、Windows10搭載のPCでWindows Updateのページを開けば、Windows11へのアップグレードの可否が確認できます。
Windows Updateのページで、最小システム要件を満たしていない旨のメッセージが表示されたら、現状のままではアップデートができません。下記のPC正常性チェックアプリを使用して、満たしていない要件を確認しましょう。
「PC正常性チェックアプリ」を利用する
「PC正常性チェックアプリ」は、使用中のPCがWindows11のシステム要件をクリアしているか総合的に検証できるツールです。アップグレードの対象となるPCかユーザー自身でも確認できるように、Microsoft社から提供されています。
アプリの入手は、Windowsのタスクバーで「PC正常性チェック」と検索し、ダウンロードする方法が簡単です。インストール後、「Windows11のご紹介」セクション内の「今すぐチェック」から、システム要件への適合性を確認できます。
要件を満たしていない項目があれば表示されるので、その内容を基にPCの状況を把握しましょう。
特に注意したい要件が、セキュリティ強化を目的にWindows11で新たに追加されたTPM2.0です。機能は搭載しているものの、有効化されていないPCもあることから、TPM2.0に非対応と表示された場合は、下記の手順でPCの設定を確認してみてください。
Windowsスタートボタンを右クリックし、一覧から「セキュリティー デバイス」を選択して、「トラステッド プラットフォーム モジュール 2.0」があれば、TPM2.0が有効です。
Windows11にアップグレードする方法

続いて、Windows11へ移行するための具体的な方法を3つ紹介します。
1.Windows Update
Windows Updateを経由したWindows11へのアップグレードは、Microsoft社が公式に推奨している方法です。次のような手順で実行します。
| 1.Windowsスタートボタンの「設定」をクリックし、「更新とセキュリティ」からWindows Updateにアクセスします。 2.Windows11へアップグレードを実行できる旨が表示されたら、「ダウンロードとインストール」をクリックしましょう。 3.ライセンス条項を確認の上、同意した後にWindows11のダウンロードとインストールが開始します。インターネット環境にもよりますが、所要時間は、数十分~2時間程度が目安です。 4.再起動を促されたら、「今すぐ再起動する」をクリックしてください。更新が完了したら、Windows11を利用できます。 |
2.インストールアシスタント
Windows11インストールアシスタントは、手動でのアップグレードを簡略化するツールです。実行時は下記を実施します。
| 1.Microsoft社のダウンロードページにアクセスして、「Windows 11インストールアシスタント」セクションの「今すぐダウンロード」ボタンを押します。 2.ダウンロードされたファイルを実行すると、ライセンス条項が表示されます。問題なければ、「同意してインストール」をクリックします。 3.PCの再起動を促す画面が表示されたら「今すぐ再起動」ボタンを押して、電源を入れたままインストールの完了を待ちましょう。更新が終わったら、Windows11が利用できます。 |
3.インストールメディア
インターネット環境につながっていないスタンドアローンPCの場合は、インストールメディアを用いてWindows11へアップグレードします。インストールメディアは、下記の手順で作成します。
| 1.Microsoft社のダウンロードページにアクセスして、「Windows11インストールメディアを作成する」セクションの「今すぐダウンロード」をクリックします。 2.ダウンロードされたファイルを実行すると、ライセンス条項が表示されます。問題なければ、「同意してインストール」を選択しましょう。 3.言語とエディションの選択ページでは、言語が「日本語」、エディションが「Windows11」と自動表示されます。言語を変えたい場合は、「このPCにおすすめのオプションを使う」のボタンを外すと、変更が可能です。 4.使用するメディアを尋ねられたら、「USBフラッシュドライブ」と「ISOファイルメディア」から選択します。USBメモリを使用するなら「USBフラッシュドライブ」、DVDを使用するなら「ISOファイルメディア」を選びます。 5.メディア作成が開始されます。作成時間は使用環境によって異なりますが、30分~1時間程度を見積もっておくと良いでしょう。USBメモリを使用する場合は、このタイミングで内部の全データが削除されるため、大切なデータは事前に移行しておいてください。 6.アップグレードしたいPCに作成したインストールメディアを接続して、Windows11のインストールを実施します。画面の指示に従ってアップグレードを完了させてください。 |
Windows11のシステム要件を満たさない場合の対応策
サポートが切れたWindows10を使用し続ければ、セキュリティレベルの低下だけでなく、他のシステムやデバイスとの互換性問題なども発生するリスクが高くなります。
既存の法人PCがWindows11のシステム要件を満たさない場合は、下記の対処を検討しましょう。
・Windows11搭載のPCへ買い替える
| Windows11搭載のPC(もしくはシステム要件を満たしたPC)へ買い替える方法です。機能や操作性、セキュリティレベルなどの向上も期待できます。 |
・別のOSへ移行する
| PCの買い替えが難しい場合は、ChromeOS、macOS、Linuxなど、別のOSへ移行する方法も考えられます。ただし、機能面やセキュリティ、互換性、コストなどの違いを理解した上で、使用環境に合ったOSを選択しなければなりません。 |
・仮想デスクトップを活用する
| Windows11の利用が可能な仮想デスクトップを活用する方法もあります。物理的なPCの利用環境にとらわれることなく、サーバー上に作成された仮想デスクトップ環境で、Windows11を利用できる仕組みです。 |
詳しくはこちらの記事で解説していますので、アップグレード以外の解決策をお探しの方は、ぜひご覧ください。
関連記事:「windows10 サポート 終了 どうなる」
まとめ
古いOSのまま使用し続けると、PCのセキュリティリスクが高まるだけでなく、互換性の低下により新しいソフトウェアやデバイスが使用できなくなる可能性もあります。ビジネス上得策とはいえないため、適切な対応策を早めに講じましょう。
アップグレードに必要なシステム要件が整ったPCを導入したい企業様は、ぜひ日本システムケアへご相談ください。Intelの第8世代CoreやAMDのRyzen 2000以降など、Windows11へのアップグレード条件を満たした機種の購入・レンタルが可能です。導入後は保守運用も行いますので、今後のアップグレード時にも迅速に対応できます。
また、不要なPCの回収も承っておりますので、買い替えに必要な工数やコストの削減も実現できます。
詳しくは下記をご覧ください。
>>日本システムケアのサービス詳細はこちら