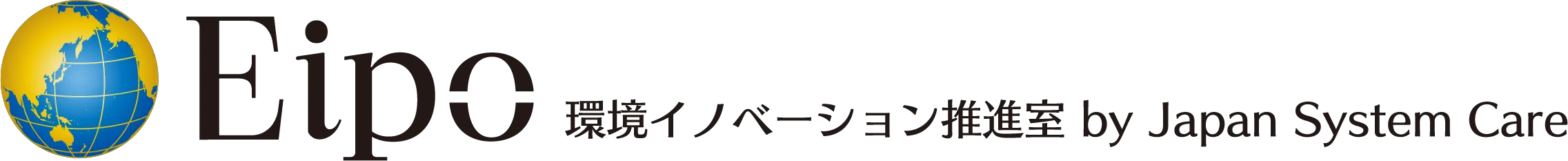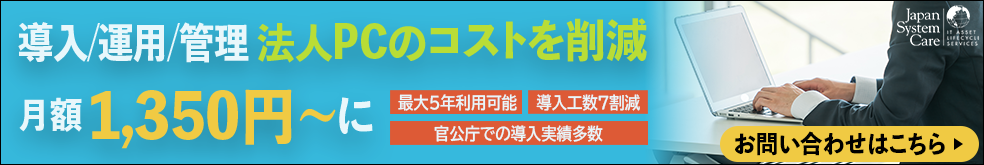ITサービスを効率的かつ高品質に運用するために欠かせないのが「ITIL」というフレームワークです。しかし、ITILとは具体的にどのような仕組みで、なぜ多くの企業で導入されているのでしょうか。
今回は、ITILの概要や誕生の背景、そして情シス部門における活用メリットや導入のポイントについて解説します。
目次
ITILとは?
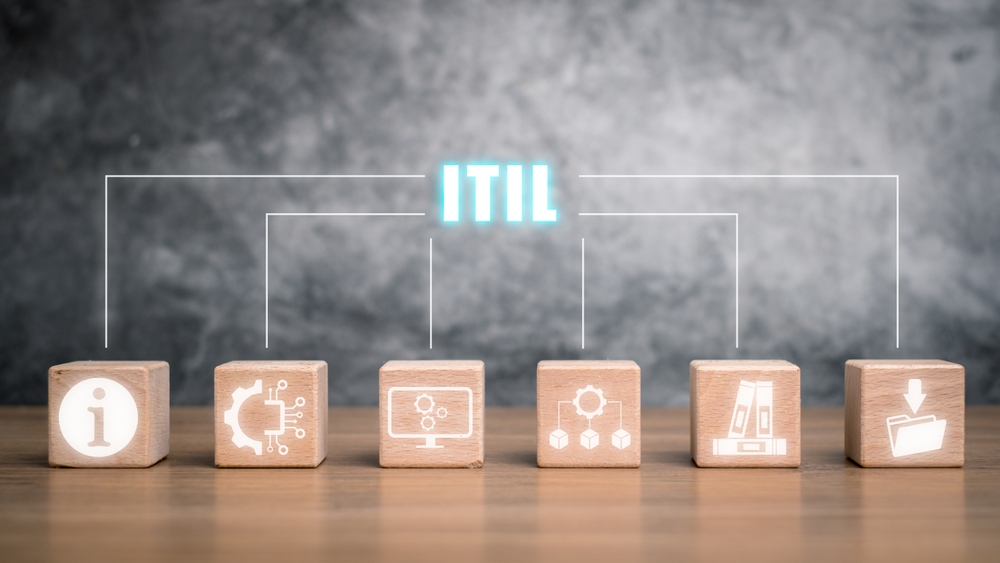
ITサービスマネジメントを考える上で欠かせないフレームワークが「ITIL」です。ここでは、その概要と誕生の背景について解説します。
ITILの概要
ITIL(Information Technology Infrastructure Library)とは、ITサービスを効率的かつ高品質に提供する方法を体系化したフレームワークです。世界中の企業や組織が導入しており、ITサービスマネジメントの事実上の標準として広く認識されています。
サービスの企画、設計、運用、改善に至るまでのプロセスを包括的に整理している点が特徴です。これを導入することで、組織は顧客満足度の向上やコスト削減、業務効率化を実現しやすくなります。
ITILが誕生した背景
ITILが誕生したのは1980年代、イギリス政府が情報システムの品質と効率性の低下に危機感を抱いたことがきっかけです。当時、公共機関や企業ではITの利用が急速に拡大していましたが、標準化された管理手法がなく、システムのトラブルやコストの肥大化が深刻な問題となっていました。
その状況を改善するために、英国政府のCCTA(Central Computer and Telecommunications Agency)がITサービス管理のベストプラクティスをまとめたのがITILの始まりです。その後、改訂を重ねながら世界中で広まり、現在では多くの企業にとって欠かせない指針となっています。
ITILの5つのフェーズ

以下では、ITILが定義する5つのフェーズについて解説します。
サービス戦略(サービスストラテジ)
サービス戦略は、ITサービスをどのように事業価値へつなげるかを定めるフェーズです。ここでは「誰に」「どのような価値を」「どのような形で」提供するのかという基本方針を策定します。
サービスポートフォリオ管理や需要管理、財務管理などを通じて、リソースの配分を決定し、組織の競争優位性を高めることが目的です。戦略がしっかりしていれば、サービス設計や運用も効率的に進められます。
サービス設計(サービスデザイン)
サービス設計は、戦略で定めた方向性を実際のサービスとして形にする段階です。ここでは、サービスカタログやSLA(サービスレベル合意書)の作成、セキュリティや可用性、容量設計などを行います。
さらに、将来的な拡張や変更にも対応できるよう柔軟性を持たせることも重要です。サービス設計は利用者の体験に直結するため、利用者視点での利便性や品質を意識する必要があります。
サービス移行(サービストランジション)
サービス移行は、設計されたサービスを本番環境へ導入し、安定的に利用できる状態にするフェーズです。変更管理、リリース管理、テストや検証を通じて、リスクを最小限に抑えながら展開を進めます。
新しいサービスや機能をユーザーへ提供する際に発生しがちな混乱を防ぎ、スムーズに稼働させることが目的です。適切な移行管理を行うことで、サービス開始後の障害発生を大幅に減らすことができます。
サービス運用(サービスオペレーション)
サービス運用は、日常的にサービスを提供・維持するフェーズであり、ITILのライフサイクルの中でも最もユーザーに直結する部分です。
インシデント管理や問題管理、アクセス管理、サービスデスク対応などが中心となり、利用者が安心してサービスを利用できる状態を保ちます。サービス運用は組織の信頼性を支える要であり、迅速なトラブル対応と安定した稼働が求められます。
継続的サービス改善
継続的サービス改善は、既存のサービスを評価し、改善点を洗い出してさらに良いものへと進化させるフェーズです。KPIや顧客満足度の測定を通じて改善すべき課題を特定し、改善策を実施します。
この活動は戦略や設計、運用すべてのフェーズにフィードバックされ、サービス全体の品質向上につながります。環境やニーズが変化し続ける中で、継続的な改善を行うことは組織の競争力維持に欠かせません。
情シス部門にITILを取り入れる重要性

基本的に ITILは「ITサービス提供者側(IT部門やベンダー)」の視点から整理されたフレームワークですが、情報システム部門にとっても有用な考え方です。以下では、情シス部門がITILを導入することで得られる3つのメリットについて解説します。
業務効率化とコスト削減
ITILを導入することで、業務の属人化を防ぎやすくなります。例えばインシデント管理や変更管理をプロセス化することで、作業の重複や無駄を削減し、限られたリソースを有効活用できます。
また、トラブルによるシステム停止を減らすことで、復旧対応にかかる人件費や機会損失を抑えられるため、コスト削減にも直結します。
トラブル対応力の向上
ITILのインシデント管理や問題管理を取り入れることで、「PCが動かない」「メールが送れない」といったトラブル発生時の対応が迅速かつ的確になります。対応手順が標準化されることで、担当者によるばらつきを減らし、サービス復旧までの時間を短縮することが可能です。
さらに、問題の根本原因を特定し、再発防止策を講じることで、同じ障害の繰り返しを防ぎやすくなります。
サービス品質の向上
「問い合わせは何時間以内に一次回答する」などSLA(サービスレベル合意)を明確化することで、従業員の信頼性や安定性が高まります。
結果として、情シス部門は単なる運用担当から、組織の成長を支える戦略的な存在へと進化できるのです。
ITILを取り入れるポイント
ITILは部署の状況に合わせた形で運用体制を整え、継続的に改善していくことが成功のカギです。以下では、ITILを効果的に取り入れるための4つのポイントを解説します。
人・仕組み・ツールをバランス良く整える
ITIL導入において重視すべきなのが「People(人)」「Process(仕組み)」「Product(ツール)」の3つ、いわゆる「3P」です。人材教育を通じて部署全体にITILの考え方を理解させると同時に、業務プロセスを標準化し、必要なITツールを導入することで、バランスの取れた体制を整えることができます。
いずれかひとつが欠けると運用が形骸化しやすいため、総合的な取り組みが不可欠です。
社内の情報を見える化して共有する
ITILの効果を高めるには、部署をまたいだ情報共有の仕組みづくりが欠かせません。インシデントや変更に関する情報を一元管理し、ナレッジとして蓄積することで、誰でも必要な情報にアクセスできる環境を構築します。
これにより、属人化を防ぎ、トラブル発生時にもスムーズな連携が可能となります。見える化された情報は、改善活動の基盤にもなります。
トラブル対応と改善を同時に進める
ITILでは、インシデント対応による即時復旧と、問題管理・変更管理による根本改善を同時並行で進めることが推奨されています。発生したトラブルを迅速に解決するだけでなく、その原因を分析し、再発防止策を講じることで、長期的に安定したサービス運用を実現できます。
この姿勢を継続することで、情シス部門は組織全体の信頼を得られるようになります。
効率化を支える専用ツールを活用する
ITILを運用に落とし込む際には、専用のITサービスマネジメントツールを導入することが有効です。例えば、ManageEngineやServiceDesk Plusなどのツールは、インシデント管理や変更管理を標準化し、日常業務の負担を軽減します。
また、レポート機能を活用すれば、改善状況の可視化やKPIの測定にも役立ちます。
まとめ
ITILを活用することで、情シス部門は効率的かつ安定したITサービス運用を実現できます。しかし、IT資産のライフサイクル全体を自部門だけで管理するのは容易ではありません。そこで有効なのが、ITの資産管理から保守・入れ替えまでを一括でサポートする「LCMサービス」です。情シスの負担軽減はもちろん、最新のセキュリティや管理体制に対応することでリスク低減にもつながります。ITILの取り組みをさらに強化したい方は、一度導入を検討してみてはいかがでしょうか。