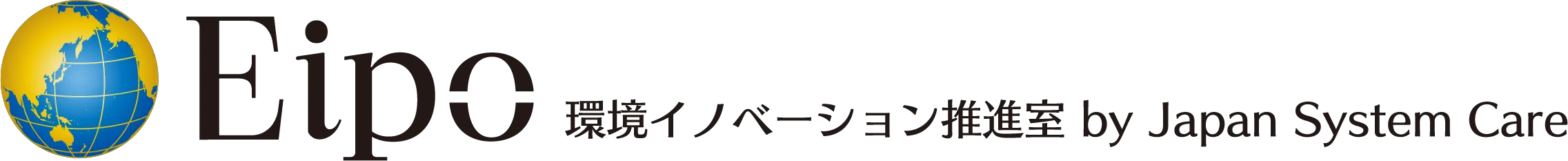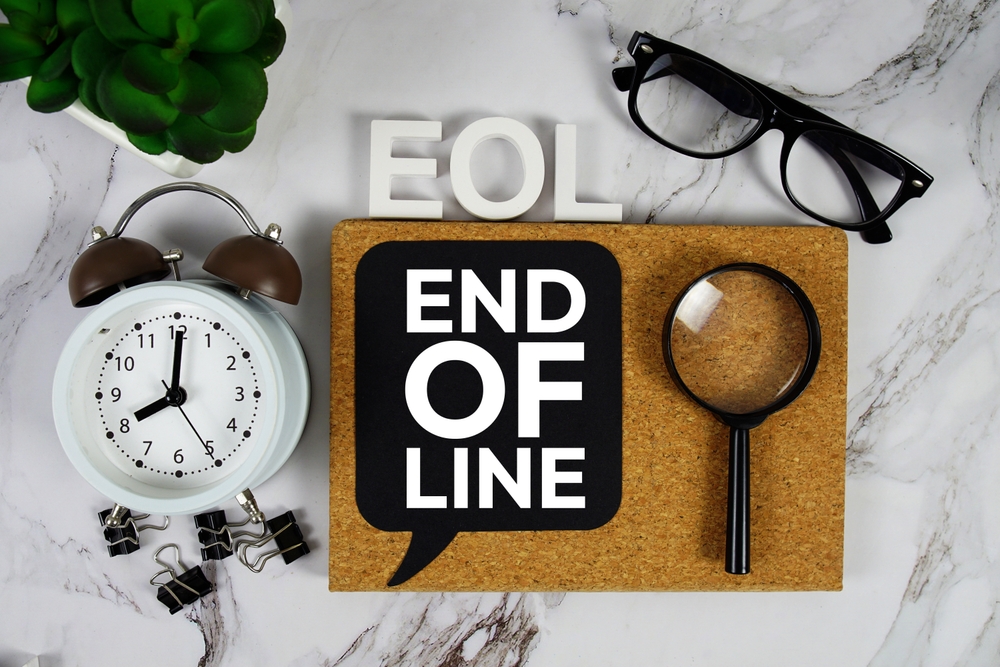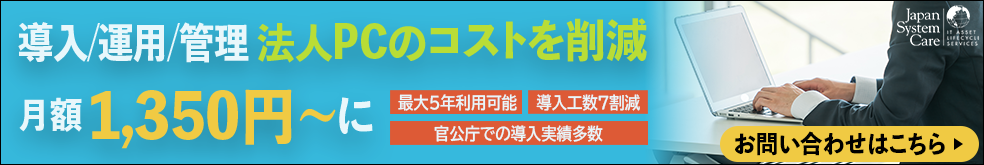EOL(End of Life)とは、製品やサービスのライフサイクルが終了し、サポートやアップデートが提供されなくなる状態のことです。EOL製品を使い続けると、セキュリティリスクや業務停止、コスト増加などの問題が発生しますが、多くの企業がその影響を軽視しがちです。
今回は、EOL対応について、そのリスクや対応策を詳しく解説します。
目次
EOLとは?

EOL(End of Life)とは、製品やサービスの生命周期が終了することを意味する用語です。
特にIT分野においては、ハードウェアやソフトウェアのサポートが完全に終了する状態を指します。
EOLはコンプライアンス要件を満たせなくなるリスクや、取引先からの信頼失墜といった経営レベルの問題にまで発展するおそれがあるため、担当部門は計画的なEOL対応が不可欠です。
EOLを放置するリスク

EOL製品をそのまま使い続けることは、企業経営に深刻な影響を与える可能性があります。ここでは、その主要なリスクを解説します。
セキュリティリスクの増加
EOL製品の継続利用は、企業のサイバーセキュリティを著しく脆弱化させ、重大なインシデントを引き起こす可能性があります。
セキュリティパッチの提供停止により、新たに発見される脆弱性への対処が不可能になります。
サイバー攻撃者はEOL製品の脆弱性を狙い撃ちする傾向があり、標的型攻撃やランサムウェア感染のリスクが格段に高まります。実際に、古いWindows OSを使い続けていた企業が大規模なサイバー攻撃を受け、顧客データが流出した事例も報告されています。
業務停止リスクの増加
EOL製品の経年劣化は、予期しない業務停止を引き起こし、企業活動に深刻な打撃を与える可能性があります。
特に基幹システムでの障害は、受注処理や在庫管理などの重要業務を完全に停止させるおそれがあります。復旧に要する時間も長期化しがちで、その間の機会損失や顧客からの信頼失墜は計り知れません。
コストの増加
EOL製品を維持する場合、長期的には新システム導入以上の費用負担が必要になる場合があります。
例えば、製造中止された部品の調達コストは市場価格の数倍に跳ね上がることが一般的です。特殊な部品では、10倍以上の価格になることもあります。
システム統合や他製品との互換性確保のための追加開発費用、セキュリティ対策の強化費用なども必要となり、総合的なTCO(Total Cost of Ownership)が予想以上に膨らんでしまいます。
競争力の低下
最新技術への対応遅れは、企業の市場競争力を根本的に損ない、長期的な事業成長を阻害する重要な要因となります。
EOL製品では新しいファイル形式やプロトコルに対応できず、取引先との円滑な情報交換が困難になります。また、AI・IoT・クラウドといった最新技術との連携もできないため、業務効率化や新サービス開発の機会を逃す可能性もあるでしょう。
EOLを迎えたときの4つの対応策

ここでは、すぐに検討すべき4つの主要な対応策について、それぞれの特徴とメリット・デメリットを詳しく解説します。
アップグレード
アップグレードは、既存製品やサービスの最新バージョンへ更新することを指します。
現在の業務フローやデータを大幅に変更することなく、最新のセキュリティパッチや新機能を利用できるようになります。
操作方法の大きな変更がないため、従業員の教育コストも最小限で済み、業務への影響も軽減できます。
ただし、ハードウェアの性能不足により新バージョンが動作しない場合や、カスタマイズした機能が新バージョンで利用できなくなるリスクも考慮する必要があります。
関連記事:「Windows11へのアップグレード条件とは?チェック方法と対応策も紹介」
移行
移行とは、現在利用中のシステムをまったく新しい製品に交換することを指します。
移行による最大のメリットは、最新技術の恩恵を最大限に活用できることです。クラウド技術、AI機能、モバイル対応など、現代のビジネス要件に適した機能を一気に導入でき、業務効率の大幅な向上が期待できます。
一方で、初期投資コストが高額になりがちで、データ移行作業や従業員研修などの準備期間も長期化する傾向があります。移行時のトラブルリスクも考慮し、十分な検証とバックアップ体制の構築が不可欠です。
延命
延命は、第三者保守サービスを活用して既存システムを一時的に運用継続することです。本格的な移行準備期間を確保するための「つなぎ」の対策として有効活用できます。
延命対応の最大の価値は、急激な変化を避けながら、十分な検討時間を確保できることです。EOL後も現在の業務を継続できるため、新システムの選定や予算確保、移行計画の策定を慎重に進められるでしょう。
ただし、保守費用は純正サポートより高額になることが一般的で、対応可能な範囲も限定的です。セキュリティパッチの提供がない場合も多く、あくまで一時的な措置として位置づけることが重要になります。
廃止
廃止は、EOL製品の利用完全停止または最小限運用へ切り替えることを指します。コスト削減とリスク排除の観点から検討すべき選択肢のひとつです。
最大のメリットは、EOL関連のリスクとコストを根本的に排除できることです。セキュリティリスクや故障リスクから完全に解放され、保守費用も不要になります。システムの複雑性も軽減され、他システムとの連携トラブルも回避可能です。
一方で、代替手段の確立が困難な場合は業務に支障をきたすリスクがあり、従業員の業務負担増加も懸念されます。廃止の判断には、該当システムの業務における重要度と代替可能性の慎重な評価が不可欠です。
EOL対応をスムーズに行うための準備
EOLへの対応を後手に回らずに行うためには、事前の計画的な準備が不可欠です。突然のサービス終了通知に慌てることなく、計画的に対応を進めるための重要なポイントを解説します。
製品ごとにEOLの情報を整理しておく
自社が保有するIT機器やソフトウェアの現在のライフサイクル段階を把握し、EOL予定日を事前に整理しておきましょう。
メーカーの公式サイトや保守契約書を確認し、主力システムから周辺機器まで網羅的に管理することが重要です。
EOL対応の優先順位付けを行う
限られた予算と時間の中で効率的に対応するため、システムの重要度、業務への影響度、セキュリティリスク、対応コストの観点から優先順位を明確化することが必要です。
基幹システムやセキュリティリスクの高い製品を最優先とし、段階的な対応計画を策定しましょう。
時間に余裕を持って早めに計画を立てる
EOL対応には調査、選定、移行作業など長期間を要するため、EOL予定日の1年以上前から準備を開始することが理想的です。
EOL対応に必要な予算を明確にする
システム更新費用だけでなく、データ移行作業、従業員研修、一時的な業務停止による機会損失まで、総合的なコストを算出しておきましょう。
早めに予算を確保しておくことで、最適な対応策の選択肢が広がり、急な価格変動リスクも回避できます。
PCの保守・運用の依頼も検討する
社内リソースが不足している場合は、専門業者への外部委託も検討しましょう。
専門知識を持つ技術者に依頼することで、社内業務への影響を最小化しつつ、安全な作業を実現できます。
またPCの保守・運用に関するご相談は、日本システムケアもお受けしております。保守運用、回収・廃棄、また次の導入支援まで、ライフサイクル全体をサポートしておりますので、PCの管理を一括で任せたい担当者様はぜひ一度ご相談ください。
まとめ
EOL(End of Life)は、IT製品やサービスのライフサイクルが終了し、サポートが終了することを意味します。EOL製品を放置することは、セキュリティリスクや業務停止、コスト増加、競争力低下などの深刻な問題を引き起こす可能性があるため、計画的な対応が求められます。
企業の継続的な成長とセキュリティを守るために、早めにEOL対応の準備をしていきましょう。