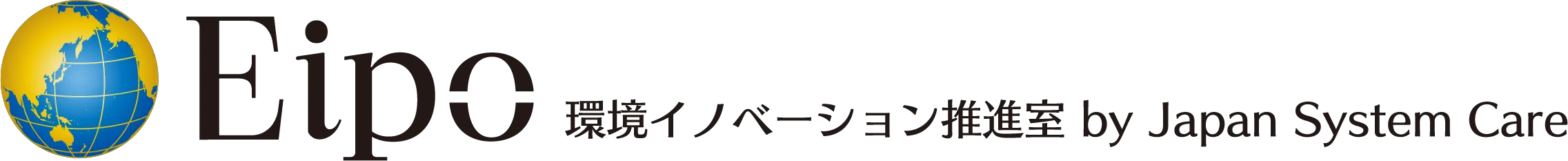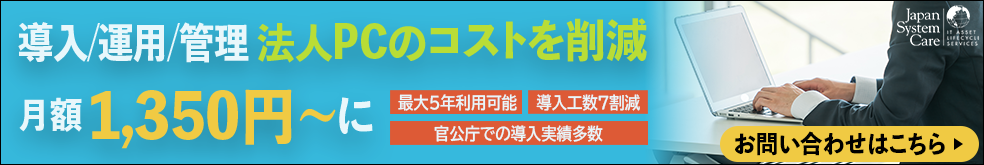テレワークの普及に伴って、セキュリティ対策は企業の大きな課題となっています。情報漏洩のリスクが高まる中、従業員一人ひとりのセキュリティ意識も重要です。
今回は、テレワーク導入時に生じるセキュリティリスクと必要な対策を詳しく解説します。
目次
テレワークにおける重大なセキュリティリスク

テレワークの導入が進む中で、最も気になるのはセキュリティ面ではないでしょうか。オフィスでの業務とは異なり、テレワークでは外部からアクセスするため、従業員の個々のセキュリティ意識や対策が大きな影響を与えます。
ここでは、テレワークにおける代表的なセキュリティリスクとその対策について解説します。
安全でないWi-Fi接続や外出先での情報漏洩
テレワーク最大のリスクは、安全が確保されていない通信環境からの情報漏洩です。
コワーキングスペースやカフェなどで提供される公共Wi-Fiは、暗号化が不十分な場合が多く、悪意ある第三者による「中間者攻撃(Man-in-the-Middle攻撃)」によって通信内容を盗み見られるリスクがあります。
実際に、公共Wi-Fiを経由した社内システムへのアクセスにより、機密情報が流出した事例も報告されています。
また、公共の場での業務は、物理的な「ショルダーハッキング」(画面を覗き見される)や会話の盗聴によって情報が漏洩するリスクも無視できません。
記録媒体の紛失による情報漏洩
テレワークでは物理的な記録媒体の管理が社内よりも甘くなりがちで、情報漏洩のリスクが高まります。
紙の資料やUSBメモリなどの可搬媒体は、通勤中や外出先での紛失・盗難リスクが極めて高く、一度失くすと取り返しがつきません。
日本国内でも毎年、USBメモリの紛失による個人情報漏洩事故が多数報告されています。
クラウドを通じた情報漏洩
テレワークの拡大に伴い、業務効率化のためにクラウドサービスの利用が増加しています。しかし、適切な管理が行われない場合、これが情報漏洩の原因となる可能性があります。
具体的には、アクセス権限の設定に不備があったり、共有リンクの管理が不適切であったりする場合、意図しない相手に情報が流出するリスクがあります。
また、従業員が承認されていない無料のクラウドサービスを業務に使用する「シャドーIT」は、IT部門が把握できない領域でセキュリティホールを生むおそれがあり、十分な注意が必要です。
関連記事:「シャドーITの対策を徹底解説!企業事例やリスクも紹介」
私物デバイスの使用による情報漏洩
テレワーク導入時の最大の懸念点のひとつが、私物デバイスの業務利用(BYOD:Bring Your Own Device)に伴うセキュリティリスクです。
私物PCやスマートフォンは、セキュリティ対策ソフトが未導入であったり、アップデート管理が不十分であったりと、さまざまな脆弱性を抱えていることが多く、マルウェア感染によるデータ流出のリスクが高まります。
また、紛失・盗難時のリモートワイプなどの対策も講じにくく、情報漏洩時の被害が拡大しやすい問題もあります。
テレワーク導入における基本的なセキュリティ対策5選

ここでは、テレワーク導入時に押さえておきたい基本的なセキュリティ対策を5つ紹介します。
関連記事:「法人PCですべき情報漏洩の対策を難易度別に紹介!紛失・盗難時の対処法も解説」
ネットワーク・通信の安全確保
テレワークでは、従業員がどこからでも社内システムにアクセスできる環境を提供することが重要ですが、同時に通信経路の安全も確保しなければなりません。
VPN(仮想プライベートネットワーク)の導入は最優先事項です。社外からのアクセスは必ずVPNを経由させ、インターネット上での通信を暗号化することで、通信の盗聴や改ざんを防止できます。
また、ID・パスワードだけでなく、SMSやアプリによる認証コードなど、「知っていること」と「持っているもの」の2つの要素で本人確認を行う二要素認証(2FA)の導入も有効です。パスワード漏洩だけでは不正アクセスができない仕組みを構築できます。
さらに、従業員の自宅Wi-Fi環境についても最低限のセキュリティ基準(暗号化方式、パスワード強度など)を設け、チェックリストによる確認を行うことで、通信の入口となる部分の脆弱性を排除することが大切です。
端末管理の徹底
テレワーク環境では、従業員が使用する端末の管理が特に重要です。
すべての業務用端末を一元管理するために、管理台帳を作成し、どの端末がどの従業員に配布されているかを把握しましょう。
また、MDM(モバイルデバイス管理)を導入し、端末状態を一元管理することで、リモートロックやデータ消去が可能になります。
さらに、OSやソフトウェアの自動アップデートを必須化し、脆弱性の放置を防ぐことが大切です。
ガイドラインの整備
テレワークを成功させるためには、従業員全員が遵守すべき情報セキュリティガイドラインを策定し、周知することが不可欠です。
例えば、USBメモリの持ち出しを禁止する、私物デバイスの業務利用を禁止するなど、具体的なルールを設けておくことが効果的です。
クラウドサービスの利用制限・権限管理
業務で利用可能なクラウドサービスを明確に定義し、未承認サービスの利用を禁止することが大切です。特に個人向け無料サービスは、セキュリティ機能が制限されていることが多いため、ビジネス向けプランの利用を推奨しましょう。
また、クラウドサービス内のアクセス権限は「必要最小限の権限」原則に基づき、役割別に細かく設定します。全従業員がすべてのデータにアクセスできる状態は避け、部署や役職に応じた適切なアクセス権限を設定することが重要です。
さらに、ファイル共有時の共有リンク設定についても明確なルールを設け、「誰でも閲覧可能」な無制限共有を禁止し、アクセス期限や特定相手限定の設定を義務付けることで、意図しない情報漏洩のリスクを低減します。
データのバックアップと障害対策
重要なデータは「3-2-1ルール」(3つのコピー、2種類の媒体、1つは遠隔地に保管)に基づき、クラウドとローカルの両方にバックアップを取ることが推奨されます。
これにより、ランサムウェア感染やハードウェア障害によるデータ消失リスクを大幅に低減できます。
また、定期的な復旧訓練も欠かせません。障害発生時に迅速かつ的確に対応できるよう、主要システムの復旧手順を文書化し、定期的に実地訓練を実施することで、実効性のある体制を構築しましょう。
バックアップポリシーは、データの重要度に応じて差別化するのも効果的です。最重要データは日次、それ以外は週次でバックアップを行うなど、頻度に優先順位を設けることで、コストと安全性のバランスを最適化できます。
テレワーク導入で見落としがちなセキュリティの盲点

テレワーク環境のセキュリティ対策というと、VPNやデバイス管理などの技術的側面に注目しがちですが、それを利用する従業員のリテラシーが低ければ、その効果は限定的です。
セキュリティポリシーの存在を知らない、または理解していても実践できていない場合、セキュリティリスクは軽減されにくいでしょう。とりわけ非IT部門の従業員には、「なぜそのルールが必要なのか」という背景理解が不足していることが多くあります。
そのため、人事部門と連携し、セキュリティ教育を研修の正式なカリキュラムに組み込むことも重要です。
組織全体の意識改革もあわせて、セキュリティ対策を考えていきましょう。
まとめ
テレワーク導入において、セキュリティ対策は非常に重要です。特に、Wi-Fi接続や私物デバイスの使用、クラウドサービスの管理などに注意が必要です。
効果的な対策として、VPNの導入、端末管理の徹底、セキュリティポリシーの整備、クラウドサービスの利用制限があげられます。
セキュリティ教育を通じて、全従業員の意識を高め、組織全体でリスクを最小化する体制を構築していきましょう。