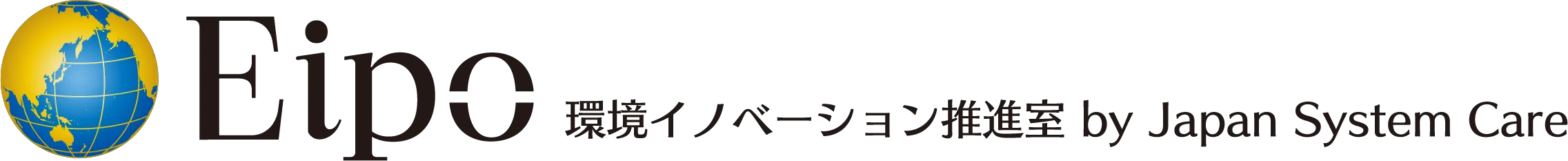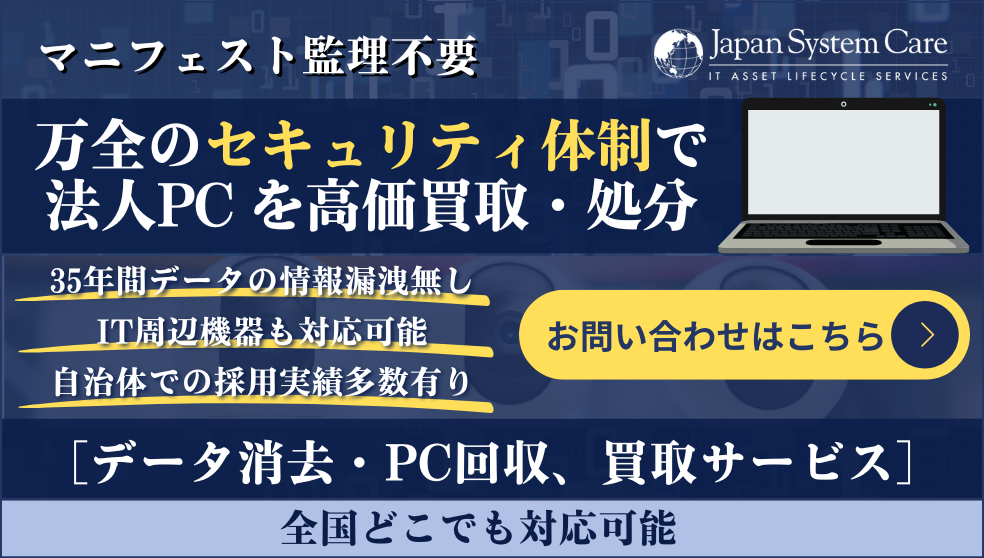サーバーは企業のIT基盤を支える重要な存在ですが、いつまで安心して使えるのか気になる方も多いのではないでしょうか。サーバーには税法上の耐用年数と実際の寿命があり、それぞれ異なる点に注意が必要です。寿命を迎えるサインやリプレースの進め方を知っておくことで、突発的なトラブルを防ぎ、安定した運用が可能になります。
今回は、サーバーの耐用年数や寿命の見極め方、更新のタイミングについて解説します。
目次
サーバーの耐用年数は?

サーバーの耐用年数には、税法上の法定耐用年数と実際の運用における寿命という2つの観点があります。それぞれの違いと具体的な年数について解説します。
法定耐用年数は5年
税法上、サーバーの法定耐用年数は5年と定められています。これは減価償却を行う際の基準となる年数で、サーバー購入費用を5年間にわたって分散して経費計上していくことになります。
この規定では、同じパソコンでも一般用途とサーバー用途で耐用年数が異なる点に注意が必要です。ただし、この法定耐用年数はあくまで会計処理上の基準であり、実際の使用可能期間とは必ずしも一致しません。
実際の寿命は3〜5年程度
一般的に、サーバーの実際の寿命は3年から5年程度とされています。法定耐用年数が5年であっても、実際には3年で寿命を迎えることもあれば、6年以上使用できるケースもあります。
負荷の高い環境下で使用されているサーバーは寿命が短くなる傾向があり、搭載されているハードディスクの種類や動作環境によっても寿命は変化します。
また、使用開始から5年を経過したサーバーは故障リスクが高まるといわれています。多くの企業では、安全性を考慮して4〜5年での更新サイクルを採用しています。
サーバーの寿命がきたときのサイン

サーバーの寿命が近づくと、さまざまな兆候が現れます。早期に気づいて対処することで、重大なトラブルを未然に防ぐことができます。代表的な3つのサインについて解説します。
パフォーマンス低下
サーバーの老朽化により、CPUや各パーツの摩耗・劣化が進むと、処理速度の低下や応答遅延が発生します。これまでスムーズに動作していたシステムが急に遅くなったり、データベースへのアクセスに時間がかかるようになったりする症状が現れます。
古いハードウェアでは最新ソフトウェアやシステム要件に対応できず、パフォーマンスが低下します。また、データ量の増加に伴ってシステム負荷も増加するため、徐々に処理能力が落ちていきます。こうした状態が続くと業務効率の低下につながり、ビジネス機会の損失にも発展しかねません。
ハードウェア障害
マザーボード、CPU、メモリ、ハードディスク、電源装置といった各パーツは、年数が経つほど摩耗や劣化が進み、不具合が発生する確率が高まります。動作が不安定になったり、予期しないエラーが頻発したりする場合は要注意です。
重要データにアクセスできなくなったり業務が完全停止したりすれば、企業として大きな損害を被ることになります。
サポート終了とセキュリティリスク
メーカーサポート終了後はトラブル発生時に技術サポートを受けられなくなる点に注意が必要です。
また、古くなったサーバーをそのまま使い続け、OSのサポートが終了すると、脆弱性をついた不正アクセスなどのセキュリティリスクを抱えることになります。外部からの攻撃を受けやすい状態が続くと、機密データの漏洩やシステムダウンなど重大な被害が発生するリスクが高まります。
サーバーリプレイスの進め方

サーバーリプレイスを成功させるためには、事前の計画から運用開始まで段階的に進めることが重要です。各ステップで押さえるべきポイントについて解説します。
1.現状の把握
まず、リプレース対象となるサーバーの現状を詳しく把握することから始めます。サーバーの台数やOSのバージョン、稼働状況、使用年数などの基本情報を整理しましょう。
また、現場の従業員からヒアリングを行い、現在のサーバーで困っていることや改善してほしい点を洗い出すことも重要です。処理速度の遅延やストレージ容量の不足、頻繁に発生するエラーなど、具体的な問題点を把握することで、新サーバーに求められる要件が明確になります。
2.計画を立てる
現状把握で整理した課題や要望をもとに、リプレースの具体的な計画を立てます。新サーバーに必要なスペックや機能、導入スケジュール、予算などを明確にしていきましょう。
リプレース後、次に交換できるのは約5年後となるため、将来の事業拡大や従業員増加なども考慮した計画が必要です。また、ソフトウェアの互換性も確認し、必要に応じて乗り換えを計画に含めます。
3.予算取りを行う
サーバーリプレイスには、小規模でも50万円から100万円程度の費用がかかります。サーバー本体だけでなく、周辺機器やネットワーク設計、構築費用、運用保守費用も含めた総額を算出しましょう。
予算を抑えるために安価なサーバーを選ぶと、後から不具合が頻発したり、スペック不足に悩まされたりするリスクがあります。一方で、過剰なスペックは予算を圧迫してしまうため、将来の成長を見込みつつも適切なバランスでの選定が重要です。
費用を削減したい場合は、クラウドサーバーへの移行も選択肢のひとつとして検討しましょう。
4.システム設計と試験運用を行う
計画で定めた要件をもとに新サーバーを設計し、必要な設定を行います。設定が完了したら、テスト環境で動作確認を実施しましょう。
この段階で注意すべきは、ホスト名やIPアドレスの変更です。これらを変更してしまうと、システム全体への反映に手間がかかり、後々の不具合の原因にもなりかねません。サーバー移行を円滑に進めるためには、可能な限り元の設定を引き継ぐことが推奨されます。試験運用で問題がないことを確認してから、本番環境への移行作業に入りましょう。
5.動作確認とフィードバック
新サーバーでの運用を開始した後は、リプレース前と同様に業務が遂行できるかを検証します。すべての部門で問題なく作業できることを確認し、必要に応じて調整を行いましょう。
万が一データの破損や消失が発生しても対応できるよう、移行前に必ず最新のバックアップを取得しておくことが不可欠です。
サーバーの寿命を延ばすポイント
サーバーの寿命を延ばすためには、定期的なメンテナンスと適切な環境管理が欠かせません。サーバーを長く安全に使用するためのポイントを紹介します。
定期的な点検・保守の体制をつくる
サーバーを長持ちさせるには、定期的な点検と保守の体制構築が不可欠です。
ハードウェアの定期点検では、冷却ファンや電源ユニット、ハードディスクなどの部品の状態を確認し、劣化や異常の兆候を早期に発見します。
また、年に数回の内部清掃を実施し、ホコリやゴミを除去することも重要です。そのほか、ソフトウェアのアップデートやセキュリティパッチの適用を計画的に行うことで、システムの安定性とセキュリティを維持できます。
適切な運用管理を行う
サーバーの寿命を延ばすには、日常的な運用管理も重要です。監視ツールを活用してシステムのパフォーマンスや稼働状況をリアルタイムで把握し、異常を早期に検知する体制を整えましょう。
また、運用ルールを明確に定め、バックアップの定期取得やログの管理、セキュリティ対策を徹底することが大切です。
設置環境を最適化させる
サーバーの物理的な設置環境は、寿命に大きく影響します。適切な温度は18度から27度、湿度は40%から60%程度が推奨されています。温度が高すぎると機器の過熱や故障につながり、湿度が高すぎると結露が発生し、低すぎると静電気が発生しやすくなります。
サーバーは前面から吸気して背面から排気するため、周囲に十分な空間を確保し、空気の対流を妨げないよう周知しましょう。また、デスクの下などの入り組んだ場所や、直射日光が当たる場所、湿気のたまりやすい場所への設置は避けることが大切です。
まとめ
サーバーを含むIT環境は、定期的な点検や適切な運用管理、最適な設置環境の維持によって寿命を延ばすことができます。しかし、日々の業務と並行してこれらを適切に管理し続けることは、専門知識と継続的なリソースを必要とする難しい課題です。
IT部門のリソースが不足している場合には、外部サービスへ依頼することも検討しましょう。例えば、日本システムケアが提供するLCMサービスでは、企業のIT資産のライフサイクル全体を一貫して管理するため、保守や入れ替えの手間を大幅に軽減できます。
情報システム部門の負担を減らしながら、最新のセキュリティ対策や管理体制でリスクを低減したい企業様は、ぜひ一度ご検討ください。