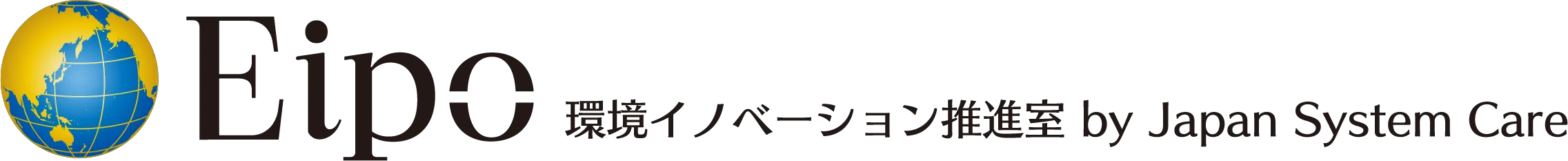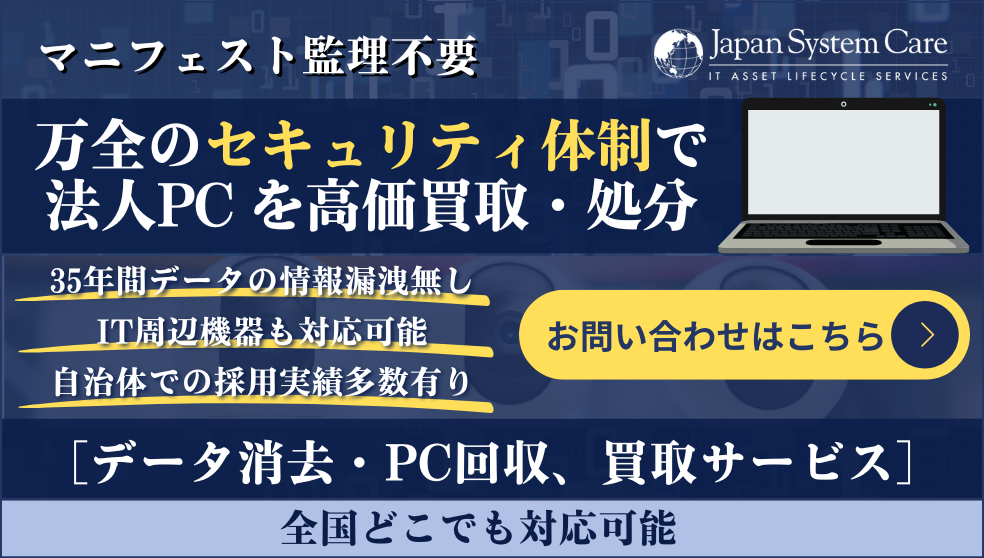モニターを長期間使用していると、徐々に画面の明るさや色合いが変わったり、ちらつきやノイズが発生したりする場合があります。これらの症状は、モニターの寿命が近づいているサインです。しかし、いつ交換すべきか、どのタイミングでチェックを始めるべきかが分からないという担当者も多いのではないでしょうか。
今回は、モニターの寿命をチェックする方法と、その寿命を延ばすための実践的なポイントについて詳しく解説します。
目次
モニターの寿命はどのくらい?

モニターの寿命について、法定上の扱いと実際の製品寿命の両面から確認していきましょう。
法定耐用年数
法定耐用年数とは、税法で定められた、企業が使用する資産(設備や機器など)の経済的寿命を示す年数のことです。
この期間内であれば、資産を減価償却し、税務上の費用として計上できます。
デスクトップPCのモニターは「その他の事務機器」として分類されており、法定耐用年数は5年です。
一方で、デジタルサイネージ(映像を用いた広告、看板、掲示板など)などの用途で使用する場合の耐用年数は3年となります。
これらの年数は税務上の基準ですが、実際の使用状況に応じて、期間が過ぎた後でもまだ問題なく使用できることもあります。
参考:国税庁「主な減価償却資産の耐用年数表」
関連記事:「PCの耐用年数は4〜5年!修理か買い替えかはどう判断する?」
製品としての耐用年数
実際の製品寿命は法定耐用年数とは異なり、モニターは一般的に15,000時間~50,000時間とされています。1日8時間、週5日使用する業務環境では、5年~15年は使える計算です。
しかし、設置環境や使用頻度によって大きく変動するため、実務上は4~5年を目安に考えるのが妥当でしょう。
モニターの寿命を確かめる4つのチェック項目

モニターが寿命に近づいているかを見極めるには、いくつかの確認事項があります。特に重要な項目について、以下に紹介します。
1.画面の明るさや色の変化はあるか
モニター寿命の初期サインとして最も一般的なのが、画面の明るさや色合いの変化です。
バックライトの劣化により、画面全体が以前より暗く感じられるようになります。また、画面に色ムラが発生したり、色が全体的に薄く見えるのも現れやすい症状のひとつです。
この症状が出た場合、まずはモニター設定の輝度や彩度を確認してみましょう。
設定を最大にしても十分な明るさが得られない場合は、バックライトの寿命が近づいている可能性が高いと判断できます。
2.画面のちらつきやノイズがあるか
モニターが寿命に近づくと、画面がちらついたり、縞模様などのノイズが発生したりする場合があります。
この症状は特に長時間使用時に顕著になり、使用者の目の疲れや作業効率の低下につながります。画面のちらつきは、液晶パーツやバックライトの劣化が主な原因です。
継続的なちらつきやノイズが発生している場合、モニターの寿命と考えて間違いないでしょう。
3.画面に線があるか
モニターの画面に黒やカラフルな線が表示される場合、それは液晶パネルの深刻な劣化が進んでいる証拠と考えられます。
これらの線は時間の経過とともに増加したり、太くなったりする傾向があり、一度発生すると修復は困難です。
ただし、同様の症状はケーブルの不良やグラフィックボードの故障でも発生することがあるため、別のモニターに接続して症状が改善するかどうかを確認することが重要です。
モニターを交換しても同じ症状が現れる場合は、PC本体や接続ケーブルに原因がある可能性が高いでしょう。
4.画面が赤みを帯びているか
長期間使用したモニターでは、画面全体が赤みを帯びる現象が起きることがあります。これはバックライトの特定の色素が他の色素より早く劣化することで発生します。
この症状が出ると、デザインやマーケティング資料の確認など色の正確性が求められる業務に支障をきたすため、早めの交換が必要です。
赤みを帯びた画面は色調整では完全に解消できないため、業務効率に影響が出る前に対応を検討すべきでしょう。
モニターをすぐに買い替えたほうが良いケース

モニターを今すぐ買い替えるべきケースとしては、以下があげられます。
・明度や彩度に明らかな劣化がみられる
・画面に黒や色のついた線が入っていて消えない
・画面に色ムラがある
・画面のちらつきやノイズがケーブル交換や接続確認を行っても解消されない
・購入から8年以上経過している(技術的な寿命に近づいている)
なお、修理という手もありますが、メーカーの保証期間を過ぎている場合は修理費用が高額になります。さらに、修理期間中の業務への影響も考えられます。
購入から3年以内の場合や、メーカーの保証期間内で無償または低コストでの修理が可能な場合を除いては、買い替えを優先すべきでしょう。
モニターの寿命を延ばすポイント
日常的な使用方法や設置環境を見直すだけで、モニターの使用期間を大幅に延長できる可能性があります。以下にモニター寿命を延ばすための具体的なポイントを紹介します。
適切な明るさで使用する
モニターの明るさ設定は寿命に直接影響します。多くのオフィスでは必要以上に明るい設定にしがちですが、これはバックライトの劣化を著しく早めます。
明るさは周囲の照明環境に合わせて40~60%の範囲で調整するのが理想的です。定期的にチェックし、作業環境に合った適切な明るさに設定しましょう。
直射日光を避ける
直射日光はモニターの大敵です。液晶パネルが紫外線にさらされると、色素の劣化が加速し、色ムラや明るさの低下を早めるといわれます。
特に窓際の席のモニターに注意しましょう。ブラインドやカーテンの設置、あるいはモニターの向きや席配置を調整するなどして、紫外線が直接当たらないよう工夫することをおすすめします。
高温多湿を避ける
モニターは温度と湿度に敏感な機器です。高温多湿の環境では内部回路の劣化が加速し、結露によるショートのリスクも高まります。
オフィスの空調設定は温度20~26℃、湿度40~60%程度を維持するよう管理しましょう。
週末や長期休暇時の空調停止による温度変化にも注意が必要です。また、モニター背面の通気口が壁や他の機器で塞がれていないことも確認してください。
こまめに電源を切る
未使用時のモニター電源オフは、バックライトの使用時間を直接削減します。昼休みや会議中、退社時には必ずモニターの電源を切ることを社内ルールとして周知すると良いでしょう。
また、省エネ設定を活用し、15分程度の未使用でスリープモードに入るよう設定することも効果的です。
そのほか、デスクトップの壁紙を暗めの色にすることも、日常的な使用時のバックライト負荷を軽減する有効な方法です。
定期的な掃除
画面の汚れやホコリは見た目だけでなく、モニターの熱放散を妨げ、内部温度の上昇を引き起こします。また、汚れが固着すると画面表面の特殊コーティングを傷める原因にもなります。
専用のクリーニングクロスと液晶クリーナーを各部署に配布し、週に一度程度の定期清掃を推奨しましょう。その際、強い力でこすらないよう注意点もあわせて周知することが重要です。
まとめ
モニターの寿命を延ばすためには、日常的な使い方や設置環境に気を配ることが大切です。明るさの設定を適切にする、直射日光を避ける、高温多湿を避ける、こまめに電源を切る、そして定期的な清掃を行うことで、モニターの寿命を長く保つことができます。
これらのポイントを実践し、従業員が快適に作業できる環境を提供しましょう。
なお、寿命がきたIT機器の買い替えを効率化したい場合は、外部サービスの導入も検討しましょう。日本システムケアでも、IT機器の調達、導入から保守運用、廃棄までライフサイクル全体をサポートするLCMサービスをご提供しております。
IT機器の管理コストや手間にお悩みであれば、以下から詳細をご覧ください。