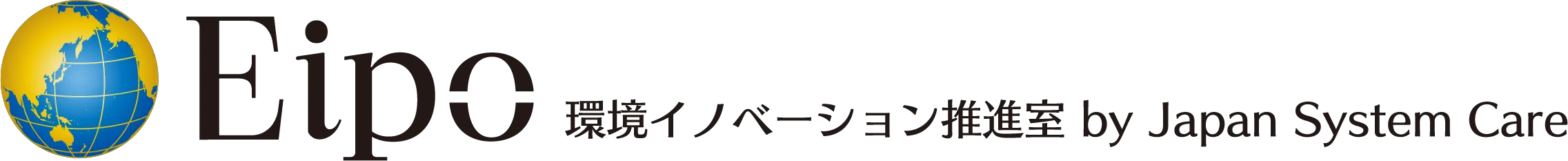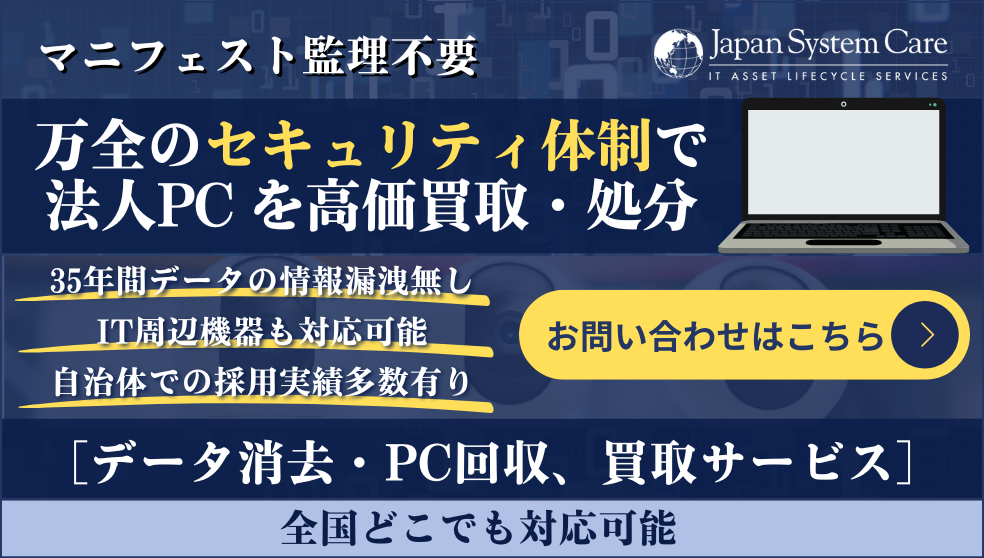法人向けPCを廃棄する際は、情報漏洩などのリスクを防ぎつつ、法律で定められたルールに則って進める必要があります。
今回は、法人向けPCを廃棄する方法や手順、廃棄のルール・注意点について解説します。
目次
法人向けPCを廃棄する方法

PCの処分については、資源有効活用促進法に定めがあります。そのため、一般ごみと同じ方法では処分できません。
法人向けPCは事業系PCとも呼ばれ、扱いは産業廃棄物です。排出業者に処理の責任があり、処分方法も決まっています。
一方、法人向けではない一般家庭から排出されるPCは、自治体で処分してもらえます。一般家庭で使われるPCには「PCリサイクルマーク」が付与されており、購入時にリサイクル代金を負担しているためです。リサイクル料金を前払いしていることから、自治体での回収に対応しています。
今回は、法人向けPCの廃棄方法を3つ紹介します。なお、法人所有のPCではなく、レンタルやリースで利用しているPCは対象となりません。レンタルやリースで借りている場合は、PCを返却するだけで済みます。
方法1|産業廃棄物処理業者へ依頼する
1つ目は、産業廃棄物処理業者を利用する方法です。
他に紹介する方法と比べて廃棄コストを抑えられるため、大量のPCを処分したい場合に向いています。PCだけでなく、プリンターやスキャナーなどの周辺機器の処分も依頼できます。
ただし、問題のある業者も存在するため、依頼する際には下記について確認しておきましょう。
・処分する地域の都道府県知事などから正式な許可を受けている
・PCなどの産業廃棄物の取り扱い許可を受けている
・データ消去証明書の発行がある
産業廃棄物処理業者に依頼する場合、産業廃棄物処分委託契約書や産業廃棄物収集運搬契約書を交わした上で、マニフェスト(産業廃棄物管理票)を交付し、5年間保管しなければなりません。
方法2|PCの回収業者へ依頼する
2つ目は、PCの回収を専門とする業者に処分を依頼する方法です。
データ消去から処分まで、まとめて依頼できるのがポイントです。手間をかけずに、コストを抑えてPCを処分できます。
ただし、依頼する回収業者はしっかり吟味するようにしましょう。データ消去に問題があり、情報漏洩などの問題が発生する可能性もあります。データ消去証明書を発行している、データの消去方法が一定の水準にあるなど、信頼性を十分に精査して業者を選択しましょう。
方法3|PCメーカーへ依頼する
3つ目は、PCの処分を製造元であるメーカーに依頼する方法です。PCの処分は1台ずつ申請する必要があるため、処分する台数が少なく、かつ同じメーカーのPCの処分をしたいときに便利です。
ただし、他社メーカー製のPCは処分できません。また、申し込みから処分までに期間がかかる点がデメリットです。産廃証明書の発行には別途料金が発生することにも注意しましょう。
法人向けPCを廃棄する手順

法人向けPCは、基本的に下記の手順で処分します。
1.処分方法を決める(産廃業者・回収業者・メーカー)
2.処分先の窓口に相談する
3.処分費用の見積もりをもらう
4.処理の委託契約を締結する
5.PCの引き渡しを行う
6.必要に応じて処分先でデータ消去が行われる
7.処分先から証明書が交付される
パソコンの処分完了後は、廃棄証明書や資産減却報告書、データ消去証明書などの証明書が処分先から交付されます。各種証明書は、法的な要件を満たすだけでなく、将来的なトラブル防止にも役立つ書類です。しっかり保管しておきましょう。
法人向けPCを廃棄する際のルール・注意点

法人向けPCを廃棄する場合に注意しておくべきポイントやルールを6つ紹介します。
資源有効利用促進法を遵守する
法人向けPCは、資源有効利用促進法により適切な処分を行わなくてはなりません。
資源有効利用促進法は、資源の廃棄の抑制、再利用、再資源化を総合的に促進する法律です。10業種69品目について、資源のリサイクルや自主回収などの規定があります。
法人向けPCも資源有効利用促進法の対象品目です。製造したメーカーが、責任をもって回収・リサイクルすることが義務付けられています。
法に定められているように、法人向けPCは適切な処分が必要です。義務を履行せず、そのまま一般ごみのように処分したり、法にもとづかない方法で廃棄したりした場合には、法律違反となり罰金刑などが科される可能性があります。
マニフェストを作成する
排出業者(企業側)がPCの処分を許可業者(産廃業者など)に依頼する場合、マニフェスト(産業廃棄物管理票)を作成し、交付しなければなりません。
マニフェストには、排出業者の氏名(または名称)や住所、産業廃棄物の種類や数量、有害物質の有無、処分方法などを記載します。基本的には用紙の記入欄にしたがえば問題ありませんが、記載漏れがないよう注意しましょう。
なお、マニフェストには、各都道府県の産業廃棄物協会で購入する紙のマニフェストと電子マニフェストがあります。電子マニフェストは、排出事業者・収集運搬業者・産業廃棄物処分業者すべてが日本産業廃棄物処理振興センターに加入している場合に限り利用できます。
また、紙のマニフェストは7枚複写が必要で、処分が完了した後は4枚手元に残ります。それを5年間保管しておかなければならない点も注意が必要です。
データをすべて消去する
法人向けPCには、事業で使用する顧客情報や企業情報、個人情報などの機密情報が保管されているため、廃棄する前にデータをすべて消去することが重要です。データを消去しないまま処分すると、情報が外部に漏れるおそれがあり、悪意のある第三者に渡れば悪用される危険性もあります。
データの消去に関しては、消去ログや専門業者に交付してもらえるデータ消去証明書を残しておきましょう。これらの証跡は、データがいつどこで消去されたかを示し、トラブル回避に役立ちます。
法人向けPCを引き渡す際には、可搬記憶媒体・リムーバブルメディア(SDカード、DVDメディアなど)の抜き忘れがないかも確認しておきましょう。
安全にデータを消去する方法について詳しく知りたい方は、こちらの記事をご覧ください。
関連記事:「PC処分で安全にデータを消去する方法!注意点も解説」
管理シールを除去し、管理台帳から削除する
法人向けPCには、会社の所有物であることを示す企業のロゴが記載されたシールや資産管理のための管理番号(資産番号)が記載されたシールが貼られているケースがあります。自社で貼付している場合は、必ず剥がしてから回収してもらいましょう。
管理番号や企業ロゴのわかるシールがそのままだと、所有元が特定されてしまいます。悪質な業者などに渡ると、不正利用されかねません。
さらに、処分するPCの情報を管理台帳や資産台帳から削除しておくことも重要です。棚卸しの際に混乱を招いてしまいます。会社で管理する管理台帳や資産台帳には各PCの詳細な情報を記載し、必要に応じて除却するなど、正確なデータが維持されるよう努めましょう。
環境に配慮する
PCを廃棄する際は、データ消去などの技術的な側面だけでなく、環境面にも配慮しましょう。環境を意識した廃棄は、会社の社会的責任を果たすことにもつながります。環境面で特に意識したいのは、下記についてです。
・環境に負荷を極力かけないPC処分方法の利用
・許認可を持っている業者へ依頼し、不法焼却、不法投棄がないように依頼する
・定期的なメンテナンスなどで既存のPCを最大限に利用して長寿命化を図る努力
・持続可能性を実現する資源循環社会に貢献できる処分方法の利用
信頼性の低い業者に注意する
法人向けPCの廃棄では、安心して処分を依頼できる業者を選ぶことが重要です。口コミや評判などを参考に、信頼に足る業者かを確認しましょう。
信頼性の低い業者にあたってしまうと、データ漏洩などのトラブルに巻き込まれる可能性があります。また、不法投棄による問題や環境への悪影響が生じるリスクも考えられるでしょう。特に、無料回収などを謳う業者には注意が必要です。
さらに、下記に該当する場合は悪質な業者の可能性があるため、十分に情報を集めてから依頼するようにしましょう。
・料金が相場に対して安価すぎる
・事業所の所在がわからない
・産業廃棄物業者の登録がない
・フリーソフトを使用している/消去方法を明らかにしていない
まとめ
法人向けPCの廃棄は、法律により拘束されるため、一般ごみのように廃棄できません。産業廃棄物処理業者、PCの回収業者、PCのメーカーのいずれかに回収してもらう必要があります。 中には悪徳業者もいて、不法投棄などのトラブルも確認されているため、安心して依頼できる業者をみつけておくことが重要です。
法人向けPCを簡単&安全に廃棄するなら!
法人向けPCを廃棄するには、情報漏洩などのリスクがあるため、安全で信頼性の高い業者を選ぶことが重要です。
現在、廃棄方法にお困りの企業様は、日本システムケアの「Re-Valueサービス」をご検討ください。
当社は1989年に創業し、資源を無駄なく再利用するための35年の実績とノウハウをもち合わせています。これまでお取引いただいた全国の企業者数は累計4,000社以上、IT機器の年間買取実績が60万台以上ございます。NIST SP 800-88準拠方式(※1)、IEEE 2883-2022(※2)などの国際ガイドラインを遵守したデータ消去を実施しており、現在まで一度も情報漏洩のトラブルはありません。
業務委託を一切利用していないのも当社の特徴です。中間業者をはさまないため、セキュリティ面でも安心して利用していただけます。全国どこでも、1台から社員が対応しておりますので、お気軽にご相談ください。
※1 NIST SP 800-88準拠方式:アメリカの政府機関であるNISTが推奨する最新のデータ消去方式のこと。
※2 IEEE 2883-2022:NISTの後継に該当する最新規格のデータ消去方式のこと。