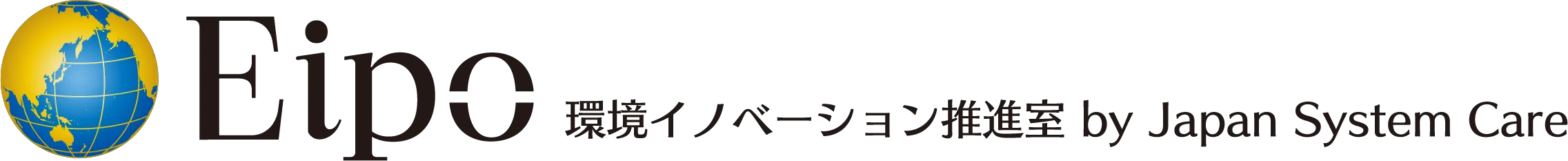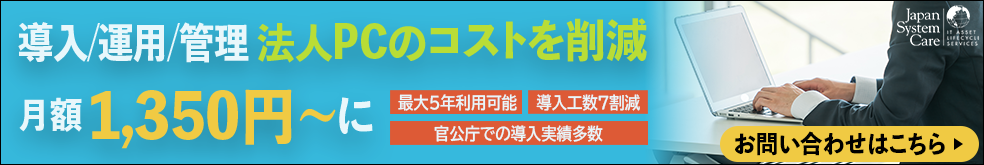情報資産管理台帳は、企業が持つPCやソフトウェア、クラウドサービス、文書ファイルなどを整理し、リスクを明確に把握するための重要な仕組みです。しかし、Excelなどでの手作業管理では漏れや重複が発生しやすく、監査やISMS更新時に大きな負担となります。
今回は、情報資産管理台帳の役割や作成の目的、具体的な方法について解説します。
目次
情報資産とは

情報資産とは、企業や組織にとって価値を持つ情報や、その関連リソースの総称です。
例えば顧客情報や契約書、人事データなどの文書ファイル、業務で利用するソフトウェアやクラウドサービス、さらに特許やノウハウといった知的財産も含まれます。また、PCやサーバー、ネットワーク機器といったハードウェアも管理対象となります。
これらは事業の継続や競争力の維持に欠かせないため、漏えいや紛失が起これば大きなリスクとなります。そのため、管理台帳を用いて所在・利用状況を正確に記録し、内部監査やISMS更新時にも対応できるよう備えることが重要です。
情報資産管理台帳とは
企業が保有する情報資産を一元的に整理したものを、情報資産管理台帳といいます。セキュリティ上のリスクを明確化するための重要な管理資料です。
PCやソフトウェア、文書ファイル、クラウドサービスなど、日々増え続ける資産をExcelなどで手作業管理していると、どうしても漏れや重複が発生しやすく、内部監査やISMS・プライバシーマーク更新時に大きな負担となります。
そのため、台帳にまとめて資産の所在・責任者・利用状況を記録することが、組織全体の情報セキュリティ強化に直結します。
情報資産管理台帳に記入すべき内容
情報資産管理台帳には、以下のような項目を網羅的に記載することが求められます。
・用途(関連業務等)
・情報資産の名称
・責任者
・利用者の範囲(閲覧権限)
・保管形態(メディアの種類)
・情報の分類区分
・保管場所(概要)
・保管期間
・評価日
・個人情報の有無
・委託の有無
・リスク評価
これらの項目を整理・記録することで、誰がどの資産を利用しているのかを明確にし、情報漏えいリスクの把握や管理体制の強化につなげられます。
また、定期的な更新を行うことで、最新の資産状況に基づいたリスク管理が可能になります。
情報資産管理台帳を作成する目的

情報資産管理台帳は、単に資産をリスト化するだけではなく、組織全体のセキュリティや効率性を高めるための基盤です。ここでは、台帳作成の5つの具体的な目的について解説します。
情報資産の可視化・現状把握
情報資産管理台帳の最も大きな役割は、組織が保有するすべての資産を網羅的に把握し、現状を「見える化」することです。
PCやソフトウェア、クラウドサービス、紙の契約書など、管理対象は多岐にわたります。Excelなどの手作業では抜け漏れが発生しやすく、内部監査の際に「どの資産を誰が利用しているか」が不明確になりがちです。
台帳を整備すれば、資産の所在・利用状況を明確化でき、管理の網羅性と正確性を担保できます。
リスク管理の強化・対策
情報資産は外部からのサイバー攻撃や内部不正、紛失といったリスクに常にさらされています。管理台帳を作成することで、各資産ごとのリスクを洗い出し、重要度や影響度に応じて優先順位をつけられます。
例えば顧客情報を含むデータベースはリスク評価を高く設定し、強固なアクセス制御や暗号化を実施するといった具体的対策につなげられます。こうした仕組みは、情報漏えい防止やインシデント対応力の向上に直結します。
コンプライアンス遵守
ISMSやプライバシーマークの取得・更新を進める上で、情報資産の管理台帳は欠かせません。規格や法令では「資産の所在や管理状況を明確に記録すること」が求められており、監査時にも確認される重要なポイントです。
正確な台帳を整備していれば、社外からの信頼性を高めるだけでなく、従業員のセキュリティ意識向上にもつながります。結果として、コンプライアンス遵守の姿勢を内外に示せるのです。
業務効率化
情報資産管理台帳を活用することで、業務効率も大きく改善されます。例えば「このソフトウェアを管理している部署はどこか」「利用者の範囲は誰までか」といった問い合わせにすぐ対応できるようになり、情報探索にかかる時間を削減できます。
さらに、資産の更新や廃棄のタイミングも把握しやすくなり、ライセンスの過剰購入や利用期限切れといったムダを防ぐことも可能です。
知的財産の保護
企業にとって特許や技術ノウハウ、顧客リストなどの知的財産は競争力の源泉です。しかし、その所在や管理状況が曖昧なままでは、不正利用や流出リスクにさらされやすくなります。
情報資産管理台帳にこれらを明記することで、どの知的財産を誰が管理しているのかを把握でき、適切なセキュリティ対策を施す基盤が整います。結果的に、企業価値を守り将来的な事業展開を支える土台となります。
情報資産管理台帳の作成方法

情報資産管理台帳を効率的に整備するには、単に資産を列挙するだけでは不十分です。網羅性と正確性を担保しつつ、内部監査やISMSの更新にも対応できる仕組みを作ることが重要です。
ここでは、4つのステップに分けて、作成方法を解説します。
STEP1|情報資産の洗い出し
最初のステップは、自社が保有する情報資産を徹底的にリストアップすることです。
PCやサーバー、ソフトウェア、契約書や顧客データといった文書ファイル、クラウドサービスなど、対象機器を洗い出しましょう。
効率的に洗い出すには、業務フローを可視化し、その過程で利用される情報資産を一つずつ確認していく方法が有効です。
STEP2|台帳フォーマットの作成
次に必要となるのが、洗い出した情報を整理・記録するための台帳フォーマットです。
IPA(独立行政法人情報処理推進機構)が公開している「中小企業の情報セキュリティ対策ガイドライン」には、無料で利用できるサンプルフォーマットがあります。これをベースに、自社の規模や業務特性に合わせてカスタマイズすると効率的です。
台帳には資産名、管轄部署、責任者、利用範囲、保管場所、リスク評価などの基本情報を記載できるようにしておくことが重要です。
STEP3|重要度の評価
情報資産を把握したら、その重要度を評価する工程に進みます。
ここで用いるのが「機密性」「完全性」「可用性」の3要素、いわゆるCIAの観点です。例えば、顧客情報を含むデータベースは機密性が高く、正確さや利用可能性も求められるため評価点は高くなります。
評価によってリスクが高い資産には、「アクセス権限の最小化」や「データ暗号化」など、具体的なセキュリティ対策を講じる必要があります。
STEP4|台帳の運用と定期的な見直し
台帳は一度作成して終わりではなく、継続的な運用と見直しが欠かせません。サイバー攻撃の手口や業務環境は日々変化しているため、最低でも年1回は台帳を精査し、リスク評価を更新することが推奨されます。
また、運用ルールを明確に定め、資産の追加・変更・廃棄のたびに台帳を更新できる仕組みを構築することが不可欠です。常に最新状態を維持していれば、ISMSやプライバシーマークの審査時に台帳の提示を求められても迅速に対応でき、社内外への信頼性向上につながります。
まとめ
情報資産管理台帳は、社内に点在するPCやソフトウェア、文書ファイル、クラウドサービスなどを整理し、リスクを把握して適切に保護するための土台となります。台帳を整備しておけば、内部監査やISMS・プライバシーマークの更新にもスムーズに対応でき、セキュリティ強化と業務効率化を両立できます。
その中でもPCは、日々の業務を支える代表的な情報資産です。適切な保守・運用が行われなければ、セキュリティリスクの温床となり、台帳に記載している情報と実態が食い違ってしまうおそれがあります。
PCをはじめとするIT機器のライフサイクル全体を正しく維持したいとお考えなら、日本システムケアへご相談ください。PCの導入から運用、保守、廃棄に至るまでを一貫してサポートしています。詳細は以下からご覧ください。