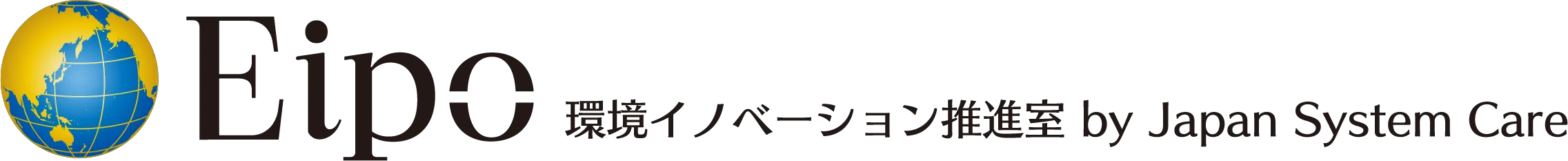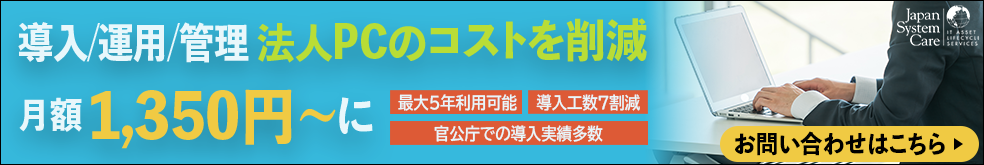EOSLとは、メーカーのサポートや保守が完全に終了する時期を指し、放置すると修理対応不可やセキュリティリスク、業務停止といった深刻な問題を招きます。特に総務・情シス担当者にとっては老朽化資産の把握と計画的対応が不可欠です。
今回は、EOSLの基本的な意味からリスク、必要な対策や準備について解説します。
目次
EOSL(End of Service Life)とは?

EOSLとは、メーカーが製品に対する「サポートや保守サービス」を完全に終了する時期を指します。
対象はIT機器やソフトウェアで、EOSLを迎えるとメーカーからの障害対応、部品提供、セキュリティパッチ配布などが受けられなくなります。
その結果、故障や障害が発生した場合に復旧までの時間が長引きやすく、業務に大きな支障をきたすリスクが高まります。業務継続や社内システムの安定稼働に直接影響するため、早い段階での理解と対応が重要です。
また、EOSLと混同されやすい用語についても整理しておきましょう。
EOL(End of Life)との違い
EOLは製品の「寿命」そのものが終了することを意味します。つまり、製品のライフサイクル全体が終わり、新たにその製品が提供されることはありません。
EOSLが「サポート終了」を示すのに対し、EOLは「製品の存在そのものの終焉」という点が大きな違いです。
EOLに到達した製品は、市場から姿を消すため、後継機種や代替製品への移行を前提にした対応が必要となります。社内にまだ稼働している該当製品がないかを把握することが重要です。
EOS(End of Sale)との違い
EOSは製品の「販売」が終了することを指します。販売が終わってもサポートや保守は続く場合が多く、すぐにリスクが高まるわけではありません。
ただし、今後新規で同じ機器を購入できなくなるため、システム拡張や同一環境の維持が難しくなります。追加導入が必要な場面で調達に制約が出る点を押さえておくことが求められます。
EOE(End of Engineering)との違い
EOEは製品の「新規開発やエンジニアリングサポート」が打ち切られることを意味します。新しい機能追加や改善が行われなくなる段階であり、現状のまま利用は可能ですが、将来的な進化は見込めません。
EOEの段階で「あとどのくらい利用できるのか」を見極め、計画的な更新を検討する必要があります。
EOSLを迎えたときのリスク・影響

EOSLを迎えた製品をそのまま利用し続けることは、リスクを抱えることにつながります。サポートや保守サービスが停止した後に起こり得る問題は多岐にわたり、業務継続やセキュリティ対策の観点からも無視できません。
ここでは、具体的にどのようなリスクがあるのかを解説します。
製品の修理対応やサポートが受けられなくなる
EOSLを迎えると、メーカーに修理やトラブル対応を依頼できなくなります。仮に部品が市場に残っていたとしても、在庫が少ないなど入手困難な場合が多く、結果として修理自体が事実上不可能になるケースも少なくありません。
不具合の修正・アップデートがされなくなる
EOSL後は、製品に不具合が見つかっても修正プログラムやアップデートは一切提供されません。これは、利用中に新たなバグや動作不良が発生しても改善の見込みがないことを意味します。
例えば、OSやソフトウェアの互換性に問題が生じた場合も、解決策は用意されず、利用者側で対応を迫られることになります。結果として、システムの安定性が損なわれ、業務に支障をきたすリスクが増大します。
セキュリティリスクが発生する
EOSLを迎えた製品は、セキュリティパッチの提供が打ち切られます。そのため、新たに発見された脆弱性が放置され、攻撃者に狙われやすくなります。
不正アクセスやマルウェア感染といったリスクは高まり、最悪の場合は社内の重要データや基幹システムが大きな被害を受ける可能性があります。個人情報や経理システムが被害を受ければ、企業全体に甚大な損害が及ぶため、放置は極めて危険です。
業務が停止するリスクが発生する
EOSL製品を利用し続けることで、システム障害が発生した際に復旧が長期化し、業務全体が停止するリスクが高まります。障害発生から復旧までに時間がかかるほど、企業活動へのダメージは大きくなり、顧客対応の遅延や売上損失といった経営課題にも直結します。
EOSLが近づいたときに必要な対策

EOSL(End of Service Life)を迎えると、メーカーによるサポートや保守サービスが受けられなくなり、業務に重大なリスクをもたらす可能性があります。社内の老朽化資産を把握し、適切な対策を講じることが求められます。
ここでは、EOSLが近づいた際に考えられる主な対応策を解説します。
機器・システムのリプレイス
一般的な対策は、EOSLのタイミングで機器やシステムを新しいものに置き換える方法です。リプレイスを行うことで、最新のサポートやアップデートを受けられるようになり、セキュリティリスクや故障時の復旧遅延といった問題を未然に防げます。
また、新製品には性能向上や新機能追加が施されているケースが多く、業務効率改善にもつながります。
ただし、導入にはまとまった投資が必要であり、予算確保や導入スケジュールの調整を早めに行うことが重要です。
バージョンアップやクラウド移行
既存の製品を完全にリプレイスするのではなく、バージョンアップやクラウド移行を行うのも有効な手段です。最新バージョンにアップグレードすれば、引き続きサポートを受けながら安定した運用が可能になります。
特にクラウド移行は、オンプレミス環境に比べて拡張性や費用対効果が期待でき、導入スピードも速い点が魅力です。
ただし、自社で利用しているアプリケーションとの互換性や既存の運用方法との整合性を慎重に検討しないと、移行後に想定外のトラブルが発生するおそれがあります。そのため、IT部門やベンダーと連携しながら段階的に進めることが重要です。
第三者保守を利用する
メーカーによるサポートが終了しても、第三者保守サービスを利用すれば継続的に修理や点検、問い合わせ対応を受けられます。
保守専門ベンダーが提供するサービスは、メーカーと比べてコストが抑えられるケースも多く、限られた予算での運用に適しています。
また、EOSLを迎えた機器でも長期的な利用が可能となり、システム移行までの時間を確保できるのも大きなメリットです。リプレイスやクラウド移行に即時対応できない場合の現実的な選択肢として検討すべきでしょう。
EOSLに備えて情シス担当者がすべき準備
システム規模が大きいほどEOSLへの対応には時間がかかるため、早めの準備が欠かせません。ここでは、担当部門が取り組むべき基本的な準備について解説します。
EOSL製品の状況把握
まずは、自社で利用しているハードウェア、OS、アプリケーションのEOLやEOSL予定日を把握することが重要です。
メーカーが公開しているサポート期限情報をもとに確認し、一覧化しておくことで、対応の優先度を判断しやすくなります。
関連部署との調整
準備を進める上では、関連部署や利害関係者との調整が不可欠です。経営層や業務部門に情報を共有し、システム切り替えのタイミングや影響範囲をあらかじめ合意しておくことが重要です。
周知不足のまま進めると、業務停止や混乱を招くリスクが高まるため、早期に社内での連携体制を築くことが求められます。
まとめ
EOSLとは、製品に対するメーカーサポートや保守が完全に終了するタイミングを指し、放置すればセキュリティリスクや業務停止の可能性が高まります。そのため、早めに資産状況を把握し、リプレイスやクラウド移行、第三者保守などの選択肢を検討することが欠かせません。
なお、社内負担を大きく減らすには、導入から運用、廃棄までを一貫してサポートしてくれる外部サービスを利用するのもひとつの手です。
例えば、日本システムケアが提供するLCMサービスでは、高品質なリユースPCの提供に加え、導入前のキッティングや導入後の保守運用、最終的な回収・廃棄までライフサイクル全体を支援しております。社内のPC管理を担当する情報システム部門や総務部門の負担を軽減したい企業様は、ぜひ一度お問い合わせください。サービス詳細は、以下リンクからご覧いただけます。