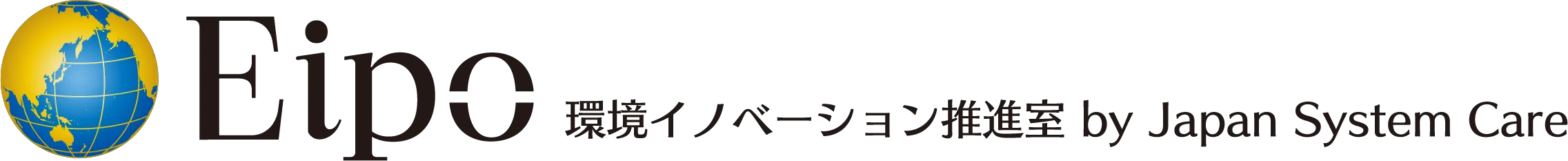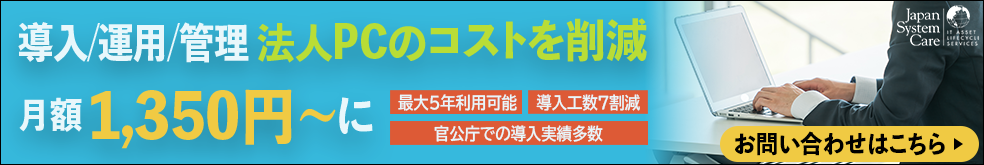会社のPC導入を担当することになり、Core i3とCore i5のどちらを選ぶべきか悩んでいませんか?プロセッサーの選択は、業務効率と予算配分を左右する重要な判断です。今回は、Core i3とCore i5の仕様の違い、それぞれのメリット・デメリット、実際の導入事例を詳しく解説します。
目次
Core i3とCore i5の仕様の違い

Core i3とCore i5の主な違いは、コア数、処理性能、ターボブースト機能などにあります。まずは、それぞれの特徴について解説します。
コア数
コア数が高いほど並列処理能力が高くなります。Core i3は4〜6コアが多く、Core i5の多くは6〜10コアを搭載しています。
Core i5の方が並列処理能力に優れているため、複数のアプリケーションを同時に動かす業務や、動画編集、3DCG制作などのクリエイティブ作業を頻繁に行う部署に向いています。
ただし、現行のCore i3は数世代前のCore i5に匹敵する性能を持っており、一般的なオフィス業務や事務作業(Excelやメール、Webブラウジングなど)は十分にこなせます。
ハイパースレッディング
ハイパースレッディングとは、1つの物理コアを論理的に2つのコアとして動作させる技術です。コアの処理単位は「スレッド」で表され、原則1コア1スレッドですが、ハイパースレッディングで1コア2スレッドにすることが可能です。
実際には1つのコアしかありませんが、コンピューターには複数のコアがあるように見せかけることで、より多くの処理を短時間で行えるようになります。
Core i3モデルはほとんどがハイパースレッディングをサポートしており、4コア/8スレッドの構成が一般的です。
一方、Core i5は第10世代以降においてハイパースレッディングをサポートしており、通常6コア/12スレッドの構成です。
ただし、第9世代以前のデスクトップ向けCore i5(特に第8〜9世代)は多くのモデルでハイパースレッディングが無効化されていました。これは、コア数を増やしながらも熱設計電力(TDP)を抑えるためと考えられています。
ターボブースト
ターボブーストは、全体の負荷に余裕がある場合に一部のコアのクロック周波数を上げて性能を向上させる技術です。
使用していないコアを一時的に停止し、その分を稼働中のコアの性能向上に振り分けることで、必要な時にピーク性能を発揮できます。
Core i5はこの恩恵を受けており、負荷の高い処理時にパフォーマンスの向上を実現します。最近のCore i3モデルにもこの機能が採用され始めていますが、全体的な性能はCore i5の方が上です。
キャッシュサイズ
キャッシュはCPU内部にある高速アクセス可能な小容量メモリで、キャッシュサイズが大きいほどCPUの処理性能は向上します。頻繁に使うデータを一時的に保存しておくことで、メインメモリからデータを取り出す時間を短縮できるためです。
Core i3のキャッシュサイズは4~12MB、Core i5は6~20MBと、Core i5の方が大きいキャッシュを搭載しています。
そのため、大量のデータを扱う業務ではCore i5の方がおすすめです。
Core i3とCore i5はどっちを選ぶべき?

結論として、導入するPCの用途に合わせて選択するのが良いでしょう。
基本的なオフィス業務(文書作成、表計算、メール、Webブラウジングなど)を低コストで実現したい場合はCore i3で十分なパフォーマンスを発揮できます。
一方、CADや動画編集、データ分析などの負荷の高い作業もストレスなく行いたい場合はCore i5を選ぶべきです。
また、故障や不具合、スペック不足が不安な場合にもCore i5が推奨されます。
そのほか、将来的な業務拡大や新しいソフトウェアの導入を見据えて、多少余裕を持ったスペックのCore i5を選択するという戦略もあるでしょう。
【使用者の口コミ】Core i3のメリット・デメリット

ここではCore i3の具体的なメリット・デメリットと実際の導入理由について解説します。
Core i3のメリット
Core i3の最大のメリットはコストパフォーマンスの高さです。最新の第14世代モデルでも2万円前後(2025年3月時点)で入手できるため、限られた予算内でPCを大量導入する場合に適しています。
Core i3のデメリット
Core i3はCore i5と比較してコア数が少ないため、複数の負荷の高いアプリケーションを同時に動かすと動作が重くなりがちです。
特に動画編集やCAD、大規模なデータ処理など、計算処理の多い業務には不向きです。こうした作業を日常的に行う部署では、作業効率が低下してしまう可能性があります。
さらに長期的な視点では、将来的に性能不足になるリスクも考慮すべきです。
ソフトウェアの要求スペックは技術の進歩によって年々高まる傾向にあり、現在は快適に動作していても、数年後には性能不足に陥る可能性があります。頻繁なPCの入れ替えが難しい企業では、余裕を持ったスペックを選択する方が安全です。
【口コミ】Core i3を選んだ理由
実際にCore i3搭載PCを導入した企業の主な理由は下記の通りでした。
・社内で使用するPCの機種を統一したいため
・導入するソフトウェアが推奨する「PassMark(パーツ性能数値)」の要件を満たしていたから
・コストを抑えつつ、必要十分な性能があるから
・一度に大量のPC入れ替えが必要で、予算内で調達できる最適な選択肢だったから
業務内容を精査し、必要十分な性能があると判断できれば、コスト効率の良いPC導入が可能です。
【使用者の口コミ】Core i5のメリット・デメリット
Core i5について、実際の使用者の声を交えながら、そのメリットとデメリットをみていきましょう。
Core i5のメリット
Core i5の最大の強みは、性能と価格のバランスの良さです。ハイエンドのCore i7やi9と比較すると比較的安価でありながら、十分な処理能力を備えています。
特に消費電力が抑えられているため、ノートPCにおいてはバッテリー持続時間の点でも優位性があります。
また、ノートPCを導入する場合、Core i5モデルは持ち運びの利便性とパフォーマンスを両立させたい場合の最適解となります。出張や会議など、社外での業務が多い従業員向けのPCとしても人気があります。
Core i5のデメリット
Core i5の主なデメリットはCore i3と比較した場合の価格の高さです。単純なコスト比較ではCore i3の方が有利であり、特に大量のPC導入を検討している場合、この価格差は総コストに大きく影響します。
【口コミ】Core i5を選んだ理由
実際にCore i5搭載PCを導入した企業からは、下記のような理由があげられています。
・以前使用していたPCがCore i5で使い勝手が良かったため、更新時も同じプロセッサーを選択した
・Core i5の方が性能が良いというイメージがあり、安心感があった
・従業員からの「PCが遅い」というクレームを避けるため、多少コストが高くても余裕のあるスペックを選択した
・将来的なソフトウェアの要求スペック上昇を見据えて、長期使用を想定した選択をした
特に新しいシステムやソフトウェアの導入予定がある場合や、さまざまな業務に対応できる汎用性の高いPCを揃えたい場合に、Core i5は安全な選択肢といえるでしょう。
まとめ
Core i3とCore i5の選択は、企業の業務内容と予算に合わせて行いましょう。Core i3は基本的なオフィス業務に十分な性能を持ちながらコストパフォーマンスに優れています。
一方、Core i5は動画編集やデータ分析などの負荷の高い作業にも対応できる汎用性を備えています。
導入前には自社の業務内容を詳細に分析し、部署ごとの要件を明確にして選択することをおすすめします。