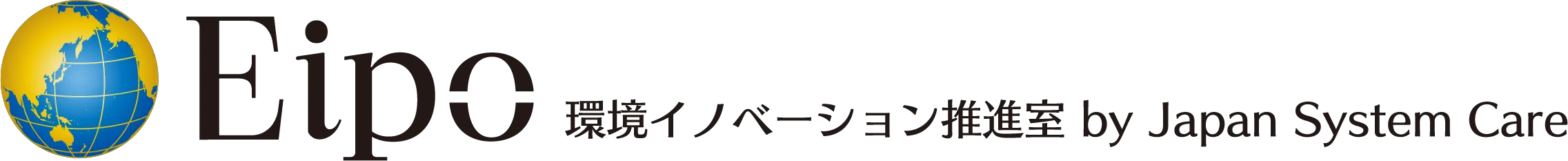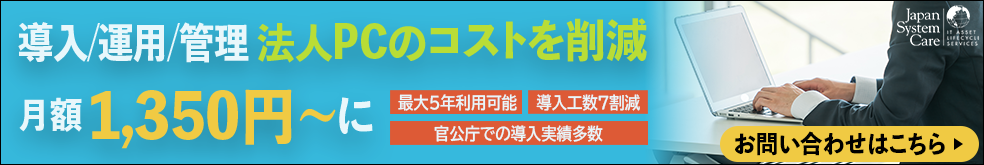PCは多くの企業にとって不可欠ですが、会計処理の中でも減価償却について悩んでいる方も多いのではないでしょうか。PCの減価償却は、取得価額や使用状況によって異なる方法が適用され、処理を誤ると企業の財務状況に大きな影響を与えます。
今回は、PCの減価償却に関する基本的なルールや方法、知っておくべき重要なポイントについて詳しく解説します。
目次
PCを減価償却するメリットとは?

PCの減価償却を適切に行うことで、購入費用を複数年度にわたって配分でき、年間の税負担を平準化することが可能です。特定の年度に大きな支出が集中することを避け、税務上の負担を均等に分散させる効果があります。
また、まとめて何台も購入した場合でも、減価償却の方法を理解していれば費用配分が明確になり、損益計算書や貸借対照表において、資産と費用がバランス良く計上されます。
会社や事業の財務状況をより正確に把握しやすくなり、計画的な設備投資や資金管理にも役立ちます。
PCの減価償却のルール

PCの減価償却は、取得価額によって異なる処理が必要です。取得価額には、PC本体だけでなく、周辺機器や送料、ソフトウェア、設置費用等の費用も含まれます。そのため、購入時には周辺機器の費用も考慮した取得価額の算出が必要です。
それでは、PCの減価償却のルールを具体的に解説します。
1台10万円未満であれば減価償却は不要
1台10万円未満で取得したPCは、消耗品として扱われるため、減価償却を行う必要はありません。10万円未満の資産は、購入費用を一括で費用計上できます。
ただし、取得価額には周辺機器や設定費用等も含まれるため、PC本体のみの金額ではない点に注意が必要です。費用計上を行うことで、償却資産税がかからず節税効果はあるものの、義務ではないため会社の経理事情に応じた対応が必要です。
また、減価償却を行うことで、金融機関から現金と同等の資産があると評価され、返済能力に対する信頼が得られます。
1台10万円以上は減価償却が必要
取得価額が10万円以上のPCは、償却資産として扱われ、耐用年数に応じて減価償却を行う必要があります。
例えば、耐用年数が4年で取得金額が16万円のPCの場合、毎年4万円ずつを減価償却費として計上します。
減価償却は、各年度で償却費を均等に配分でき、一度に費用が計上されることを抑え収益とのバランスを保つことが可能です。
PCの減価償却の方法

減価償却には、3つの方法があげられます。
・通常の減価償却
・一括減価償却資産
・少額減価償却資産の特例
それぞれ詳しく解説します。
通常の減価償却
通常の減価償却では多くの場合、「定額法」と「定率法」という2つの減価償却方法を適用します。
ここでは、以下の条件で減価償却の方法を解説します。
償却方法:税務上定められたPCの耐用年数に応じて償却
(ただし、年の途中で購入した場合は、月割計算が必要)
定額法
定額法とは、毎年同じ金額を資産から償却処理する方法です。通常、個人事業主が使用します。取得価額を耐用年数で割った金額を毎年償却する点が特徴です。
30万円のPCの場合、以下の計算式で償却額を算出できます。
75,000円 – 1円 = 74,999円(4年目)
※1円は備忘。廃棄をはじめ、該当資産が無くなったときに会計処理
定額法は毎年同じ金額を償却するため、経費の予測が立てやすいメリットがあります。
定率法
定率法とは、毎年同じ割合を資産から償却処理する方法です。通常、法人が使用します。PCの場合、定率法の償却率は0.5であり、1年間に取得した金額の半額を計上できます。
30万円のPCの場合の計算式は、以下の通りです。
2年目:15万円 × 0.5 = 75,000円
3年目:75,000円 × 0.5 =37,500円
4年目:37,500円 – 1円 = 37,499円
1年目に取得価格の半額を費用計上できます。未償却残高に0.5を掛けた金額を毎年償却していく点が特徴です。最終年度は定額法と同様に1円の簿価を残して会計処理をします。
定率法を適用すれば、初年度に多くの減価償却費を計上できるため、節税効果が高くなります。
一括償却資産|10万円以上20万円未満のPC
一括償却資産とは、PC1台あたりの取得価額が10万円以上20万円未満のPCに適用できる減価償却方法です。3年間で均等に償却処理を行い、費用計上できます。
通常のPCの償却年数は4年です。しかし、一括償却資産は3年で償却を完了できるため、より早く費用化できます。
一括償却資産の特徴は、購入時期に関わらず、購入年度内に3分の1の金額を費用として計上できる点です。つまり、年度末近くに購入した場合でも、月割計算をする必要がなく、購入年度に3分の1の金額を費用計上できます。
一括償却資産を適用すれば、1年あたりの費用計上額が増加するため、節税効果が高くなります。
少額減価償却資産の特例|10万円以上30万円未満のPC
少額減価償却資産の特例とは、中小企業者等が一定の条件を満たす場合に利用できる税制優遇措置です。以下の条件にあてはまれば、適用できます。
・PC1台あたりの取得価額が10万円以上30万円未満
・青色申告をしている中小企業
・資本金または出資金が1億円以下の法人(株式会社以外の場合)
・常時使用する従業員数が500人以下
この特例を適用すれば、対象となるPCの取得価額を取得した年度内に一括で費用計上できます。分割払いで購入した場合でも、全額を一括で費用計上可能です。
ただし、注意点として、1事業年度あたりの取得価額の合計額が300万円を上限とします。詳しくは、国税庁のホームページで確認することをおすすめします。
PCの耐用年数

PCの耐用年数は、国税庁によって定められています。一般的なPCの法定耐用年数は4年です。耐用年数は、減価償却の計算や資産の管理において重要な指標となります。
ただし、すべてのPC関連機器が同じ耐用年数ではありません。用途や種類によって、以下のように異なる耐用年数が設定されています。
・一般的なPC:4年
・サーバー用PC:5年(電子機器その他に分類)
・ディスプレイなどの周辺機器:5年(電子機器その他に分類)
出典:国税庁「主な減価償却資産の耐用年数表」
上記の耐用年数を基準に、企業は適切な減価償却計算を行い、PCの更新やリプレイスのタイミングの判断材料にできます。
PCの減価償却で知っておきたいこと
PCの減価償却には、通常の新品購入時の処理以外にも知っておくべきことがあります。以下に4つ紹介します。
PCの金額に消費税を含めるかの判断について
PCの金額に消費税を含めるかどうかは、会社が「税込経理」と「税抜経理」のどちらを採用しているかで変わってきます。
消費税込みの売り上げが1,000万円に満たない会社(=免税事業者)では、消費税の納付義務が免除されているので税込経理で簡易的に処理をすることが多いです。
税込経理では全額で、税抜経理なら税抜き金額で固定資産に計上するかどうかが決まります。
具体的には、税込経理を採用している会社では消費税込みの金額で10万円以上かどうかを判断し、税抜経理を採用している会社では消費税を除いた本体価格で判断することになります。
PCを修理した場合の計上について
PCを修理・改修して使い続ける場合、費用の会計処理方法は修理内容と金額によって異なります。
修理・改良費が20万円未満の場合は修繕費として一括で経費計上できます。これは、国税庁が「少額又は周期の短い費用」と定義しているためです。ただし、以下の3点には注意が必要です。
・修理によりPC機能の向上や使用可能期間の延長などがある場合、資本的支出として扱う必要がある
・20万円以上の修理費用であっても、おおむね3年以内の周期で行われている場合、修繕費として経費計上できる
・修理費用が60万円未満、または前期末取得価額の10%以下の場合、修繕費として処理できる可能性がある
修繕費として計上できる場合は、年度の経費として一括で処理できるため、節税効果が期待できます。一方、資本的支出と判断された場合は、PCの価値増加分として資産計上し、減価償却を通じて複数年にわたって費用化します。
未使用のPCの減価償却について
未使用のPCは減価償却資産ではありません。理由は、減価償却費が購入時ではなく、実際に使用を開始した時点から発生するためです。つまり、PCを購入しただけでは減価償却の対象とはならず、使用開始まで減価償却費を計上できません。
未使用のPCは、代わりに資産勘定の「貯蔵品」として計上します。これにより、購入したPCを適切に会計上で管理ができます。
中古のPCを購入した場合の耐用年数について
中古のPCを購入した場合、耐用年数は新品のPCとは異なる方法で計算します。中古PCの耐用年数は、使用期間を考慮して以下のように算出します。
耐用年数を経過していないPC:(耐用年数 – 経過年数)+(経過年数 × 20%)
※計算結果は1年未満の端数を切り捨て、2年未満となった場合は2年
この計算方法により、実際の使用可能期間を反映した適切な耐用年数を設定できます。
負担軽減を考えるならPCのレンタルも検討しよう!
PCの導入を検討する際、購入以外にもレンタルという選択肢があります。レンタルを利用することで、経費処理の簡素化や節税効果を期待できるため、多くの企業が注目しています。
PCをレンタルする場合の経費処理の方法
PCをレンタルした場合の勘定科目は「賃借料」として処理します。レンタルサービスを使ってPCを借り受けた場合、その機器の所有権はレンタル会社にあるため、固定資産としてカウントされず、レンタル料は基本的に経費扱いとなります。
レンタルの場合の仕訳例は以下のようになります。
<PCのレンタル料8千円を振り込んだ場合>
借方 賃借料 8,000円 | 貸方 普通預金 8,000円
PCをレンタルするメリット
レンタルの最大のメリットは、減価償却が不要で経費処理が簡素化されることです。通常、PCを購入して会社で所有する場合、台数が多い上に償却費用は導入時期によって変動することから、会計処理は煩雑になりがちです。
しかし、PCを購入ではなくレンタルすることで、導入費用は基本的に月々定額であるため、費用変動が起こりにくくなります。
また、固定資産税の課税を回避できる点も大きなメリットです。会社の減価償却が必要な固定資産が150万円以上になると、固定資産税の徴収対象となり、償却資産に固定資産税が1.4%ほど課税されることになります。PCをレンタルすれば固定資産税の課税を回避できるため、結果的に節税につながります。
また、レンタルには初期コストを大幅に抑えられるメリットもあります。PCのレンタルは利用期間に応じて料金を支払うため、購入する場合に比べて初期コストが低い傾向にあります。レンタルしているPCが故障したとしても、基本的にレンタル会社が修理費用を負担してくれるため、トータルコストも大幅に削減できます。
企業の状況や利用目的に応じて、購入とレンタルを使い分けることで、より効率的な経費管理と節税効果を実現できるでしょう。
まとめ
PCの減価償却は企業の会計と節税対策に重要な役割を果たします。取得価額で処理方法が変わり、10万円未満は一括経費計上、30万円以上は通常の減価償却が必要であり、耐用年数は一般的に4年です。
節税には安価なPCレンタルも効果的です。日本システムケアではレンタルや購入を59,400円(税込)から提供しております。導入や管理のご相談も承りますので、なるべく節税効果を高めたいとお考えの企業様は、ぜひ一度ご相談ください。サービス詳細は、以下リンクからご覧いただけます。